Useful Informationお役立ち情報
- 【グッドラーニング!】ホーム
- お役立ち情報
- 運送会社は要注意!労働基準監督署の監査と刑事罰リスクを徹底解説
運送会社は要注意!労働基準監督署の監査と刑事罰リスクを徹底解説
トラック軽貨物安全教育
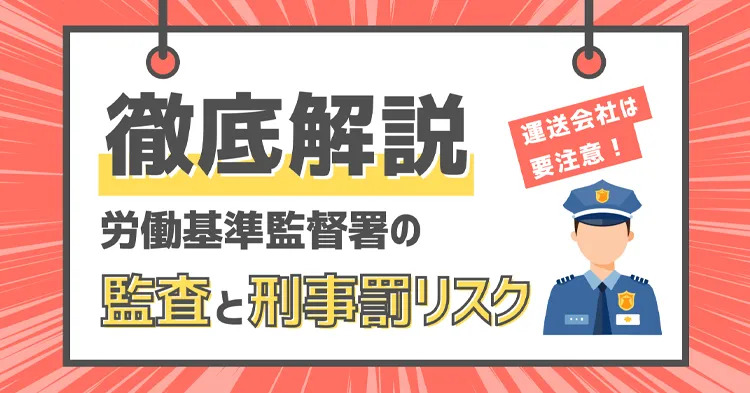
「監査に来るのは運輸支局だけ」―そんな思い込みが命取りになるかもしれません。2024年4月の法改正により「改善基準告示」の違反が刑事罰の対象になりました。労働基準監督署の監査では、悪質な場合は書類送検や罰金刑、さらには実刑判決が科される可能性があります。
今回は国交省と厚労省の改善基準告示を対象とした監査の違い・刑事罰のリスク・運送会社が取るべき対応策について解説します。
- 監査を実施するのは運輸支局だけではない!
- 2024年4月以降、処分は「確実に重く」なった
- 運輸支局の監査で違反が発覚した場合
- 労働基準監督署の監査で違反が発覚した場合
- 改善基準告示違反「4つの刑事責任ルート」
- 運送会社が今すぐ確認すべき「6つのポイント」
- まとめ
監査を実施するのは運輸支局だけではない!

「運送会社の監査=運輸支局」と思っていませんか?改善基準告示の遵守状況は国交省と厚労省の監査ポイントです。
国土交通省と厚生労働省
国土交通省は主に「交通の安全」と「交通秩序の確保」、厚生労働省は「国民の健康」や「労働環境の確保」を所管しています。改善基準告示、正式名称「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の遵守状況は、交通安全の観点と労働者の健康確保の両面から「運輸支局(国土交通省管轄)」と「労働基準監督署(厚生労働省管轄)」による監査の対象になっています。
参考:厚生労働省「トラック運転者 労働時間等の改善のための基準学習テキスト」
二重構造の監査体制
運輸支局と労働基準監督署は互いに情報連携して監査を行います。また改善基準告示違反が発覚した場合は相互に通報を行います(相互通報制度の実施)。
●監査主体:運輸支局
主な監査内容:点呼・乗務割当・安全教育・運転者台帳等の運行管理全般
●監査主体:労働基準監督署
主な監査内容:労働時間、休日、36協定、時間外労働や賃金など労務管理全般
参考:厚生労働省「自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導・送検等の状況」
2024年4月以降、処分は「確実に重く」なった

2024年4月1日から改善基準告示の改正が施行され、時間外労働は年960時間に明確に規制されました。これにより、違反は労働基準法に抵触することとなり、重大な事案は書類送検や罰金刑の対象となりました。
以前(~2024年3月末)までの状況
「改善基準告示」には法的拘束力がないとされていました。
「告示」は努力義務的な性格と解釈されることもあり、拘束時間や運転時間を多少超過しても、刑事責任を問われることはほとんどありませんでした。そのため、重大な違反があった場合でも、処分は「是正勧告」や「事業改善命令」などの行政指導が中心であり、書類送検されるケースはまれだったのです。
2024年4月からの変更点(現在)
2024年4月1日:自動車運転業務にも時間外労働の上限規制(年960時間)が適用
これにより、改善基準告示違反が労働基準法第36条(時間外・休日労働協定)、第32条・40条(法定労働時間)等に違反する行為として法的拘束力を持つ形で明確に扱われるようになり、以下のように処分が重くなりました。
| 項目 | 旧制度(~2024年3月) | 新制度(2024年4月~) |
|---|---|---|
| 時間外労働の上限 | 上限なし(適用除外) | 年960時間に制限(自動車運転業務にも適用) |
| 法的拘束力(改善基準告示) | 主に行政指導のみ(努力義務扱い) | 実質的に法令違反として扱われる(労働基準法違反) |
| 処分の対象者 | 主に法人のみ | 法人+個人(経営者、運行管理者も対象) |
| 刑事責任(書類送検) | 原則なし(例外的に送検) | 悪質なケースでは積極的に送検(全国で送検事例が増加) |
| 監査の厳格さ | 任意監査中心 | 合同監督・監査(厚労省と国交省)強化中 |
参考:
厚生労働省「自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導・送検等の状況」
厚生労働省「労働基準法第36条(時間外・休日労働協定)について」
厚生労働省「法定労働時間」
運輸支局の監査で違反が発覚した場合

運輸支局による監査は運行管理体制を重視。そのなかで改善基準告示違反が発覚した際は行政処分が科され、重大な事案では労働基準監督署へ通報される可能性があります。
運輸支局の監査ポイント
運輸支局の監査では改善基準告示について以下の点が重点的に確認されます。
- 勤務時間・乗務時間・休憩時間・休息期間が改善基準告示に違反していないか
- 点呼記録、運行記録計、運転日報の記録が整合しているか
- 運行管理者による労務管理が適切に行われているか
運輸支局の監査で違反が発覚した場合は行政処分の対象となります。
運輸支局の監査で違反が発覚した場合の行政処分
行政処分は違反内容の程度(点数制)によって決定されます。
| 違反内容の程度 | 行政処分の例 |
|---|---|
| 軽微な違反 | 指導・警告 |
| 中程度の違反 | 事業停止(〇日車など) |
| 悪質な違反 | 事業許可の取消し |
- 運輸支局の監査では、運送会社に対して事業停止などの行政処分が下されますが、直接刑事罰に結びつくことはありません。ただし、運輸支局の監査で悪質な改善基準告示違反が判明した場合、労働基準監督署や警察に通報され、刑事手続きに移行することがあります。
労働基準監督署の監査で違反が発覚した場合

一方、労働基準監督署の監査は「臨検監督」と呼ばれ、臨検監督で改善基準告示違反が認められた場合、行政処分ではなく「刑事処分」として以下の流れで対応が進みます。
是正勧告、指導票の交付
まずは是正勧告書または指導票が交付され、改善の指示がなされます。期限内に是正を完了しその内容を報告すれば、それ以上の処分に進むことはありません。
書類送検の可能性も
改善されない場合、または違反内容が悪質・重大であると判断された場合は労働基準法違反(刑事罰)として書類送検されるケースがあります。
- 労働基準法第119条に基づき、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
出典:
厚生労働省「労働基準法」
ベリーベスト法律事務所「労働基準監督署に通報されたらどうなる?」
改善基準告示違反「4つの刑事責任ルート」
改善基準告示違反は、労基署の臨検監督、運輸支局監査、交通事故による警察介入、労働者通報など、複数の経路を通じて刑事責任を問われる可能性があります。監査主体と適用法令の組み合わせによるリスクを再確認しましょう。
① 労働基準監督署(臨検監督 → 書類送検)
- 改善基準告示違反や労働基準法(第32条・第36条・第40条)違反が臨検監督で認定されると →
- 是正勧告・指導の後、違反が改善されず「重大かつ悪質」と判断されると、労働基準法第102条に基づき検察に報告 → 書類送検 →
- 労働基準法第119条(刑事罰:6か月以下の拘禁または30万円以下の罰金)による処分
② 警察・検察(交通事故 → 刑事告発)
- 過労運転や長時間拘束による交通事故で死亡・重傷が発生した場合 →
- 業務上過失致死傷罪(刑法第211条)や、道路交通法第75条1項4号「過労運転下命罪」(使用者に対し過労状態での運転を命じた罪)に問われ、刑事裁判の対象となることがあります。
- 2006年の大阪近郊の死亡事故では、運送会社社長と運輸課長に懲役刑(当時)が言い渡されました
③ 運輸支局→ 労基署 相互通報ルート
- 運輸支局による監査で、運行管理の観点から改善基準告示違反が発覚→
- 労働基準監督署へ通報(相互通報制度)→ 労基署による臨検監督に移行
- 上記①の労基ルートへ
④ 労働者(本人・労働組合等)による通報・告訴ルート
- 労働者本人または労働組合など第三者が、36協定違反や未払い賃金などを労働基準監督署に告訴・告発(労働基準法第104条・労働安全衛生法第97条)した場合 →
- 上記①の労基ルートへ
| ルート | 起点 | 適用法令 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署 | 臨検監督 | 労働基準法第32条・36条・40条・119条等 |
| 警察・検察 | 過労運転による交通事故・死亡事故 | 刑法第211条(業務上過失致死傷罪) 道路交通法第75条1項4号「過労運転下命罪」 |
| 運輸支局 (※上記2者に通報・送検依頼) |
一般監査・指導監査など | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項の規定に基づく事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(平成13年 国土交通省告示 第1365号) |
| 労働者 (※労働基準監督署に通報) |
違法な労働 | 労働基準法第104条第1項、労働安全衛生法第97条第1項 |
参考:
法務省「業務上過失致死傷」
厚生労働省「労働基準法」
国土交通省「貨物自動車運送事業輸送安全規則第三条第四項」
運送会社が今すぐ確認すべき「6つのポイント」

日々の運行管理や労働時間管理で、不適切な実態があると改善基準告示違反に問われます。2024年4月に改正された改善基準告示のポイントを正しく理解しておきましょう。そして内容が守られているか、記録として正しく管理されているか、事業者は確認を怠ってはなりません。
| ①1日の拘束時間 | 15時間が限度 |
|---|---|
| ②1ヶ月の拘束時間 | 284時間が限度(36協定時310時間) |
| ③休息期間 | 勤務終了後に継続9時間以上 |
| ④運転時間 | 2日平均で1日9時間以内、2週平均1週44時間以内 |
| ⑤休日 | 休息期間9時間+24時間の継続33時間を下回らない |
| ⑥時間外労働 | 年960時間が限度(36協定要) |
参考:厚労省 トラック運転者の労働時間等の改善基準告示のポイント
記録の整合性は「運行記録計・運転日報・勤務表・点呼記録」などが一致しているかによって判断されます。
まとめ

知らなかったじゃ済まされない!
「改善基準告示が変わったのは知っているけど内容はよく知らない」「事故を起こさなければ大丈夫」という考えは通用しません。今や改善基準告示違反は「法令違反」として明確に取り締りの対象となっています。運輸支局の監査にとどまらず、労基署の臨検監督、事故が起きれば警察ルート、そして労働者から労基署への通報等で刑事責任を問われることになります。
対応の第一歩は「正しい理解」と「記録の整備」
「改善基準告示違反」に問われないためにしっかりとその内容を理解し、関係記録を正しくそろえておきましょう。
- 労務管理、運行管理は改善基準告示の内容に合致しているか?
- 運行計画や配車計画は現実的に守れる内容か?
- 休憩、休息、休日は形式だけでなく正しく与えられているか?
- 36協定は内容と実態が合致しているか?
- 記録類の整合性がきちんと取れているか?
そして何より大切なのは「管理者はもちろん、従業員全員が改善基準告示を正しく理解し実践すること」です。しかし改善基準告示の内容は複雑で、覚えるのはなかなか難しいのが現実です。そのようなときに役立つのがeラーニングの活用です。
「グッドラーニング!」なら、パソコン・スマホで自分のペースで必要な知識を学べます。改善基準告示について「基礎編」「復習編」「応用編」に分けて詳しく解説しており、各講座の理解度チェックテストで知識の定着を促します。スキマ時間に国交省の法定教育を履修できるので、忙しい運送会社の安全教育にもお勧めのツールとなっています。ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。
当社の記事・お知らせに関する注意事項
- 最新の法改正・制度改正が必ずリアルタイムで記事に反映されているわけではありません。
- 情報を掲載するにあたり、事実と相違がないように注意しておりますが、絶対の正確性をお約束しているわけではありません。
- 掲載された情報の利用により何らかの損害が生じたとしても、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

