Useful Informationお役立ち情報
- 【グッドラーニング!】ホーム
- お役立ち情報
- 貸切バスの乗務員教育とは?安全教育の基本を解説
貸切バスの乗務員教育とは?安全教育の基本を解説
バス安全教育
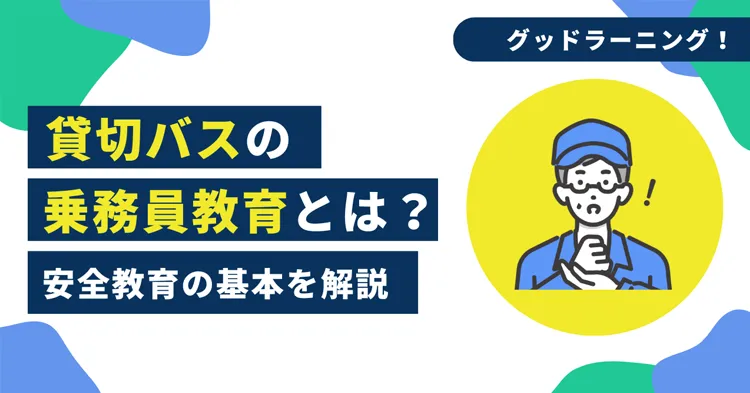
貸切バスの乗務員教育とは?安全教育の基本を解説!貸切バスの安全運行を実現するために欠かせないのが「乗務員教育」です。重大事故を防ぐには、単に運転技術だけでなく、安全意識の継続的な向上が求められます。今回は、法定13項目(指導監督指針)の内容や特定の運転者に対する特別な指導、乗務員教育をスムーズに行う方法などをわかりやすく解説!ぜひ参考にしてみてください。
- 貸切バスの乗務員教育(安全教育)は義務
- 【年間教育】法定13項目(指導監督指針)
- 1.事業用自動車を運転する際の心構え
- 2.事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
- 3.事業用自動車の構造上の特性
- 4.乗車中の旅客の安全を確保するために留意すべき事項
- 5.旅客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項
- 6.運行路線・経路における道路及び交通の状況
- 7.危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
- 8.運転者の運転適性に応じた安全運転
- 9.交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法
- 10.健康管理の重要性
- 11.安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法
- 12.ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転
- 13.ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリ・ハット体験等の自社内での共有
- 年間教育計画表・乗務員教育記録簿の作成と保存も義務
- 特定の運転者に対する特別な指導
- 貸切バス乗務員の教育方法は何がある?
- 貸切バスの乗務員教育はグッドラーニング!
- まとめ
貸切バスの乗務員教育(安全教育)は義務

貸切バスなどを運行する「旅客自動車運送事業者」には、運転者に対して定期的に「指導・監督(教育)」を行う法的義務があります。これは、道路運送法や運輸規則に基づく重要なルールです。特にバスの運転は、大型車を操作しながらさまざまな地理や天候、道路環境の中でお客様の安全を守るという高い技術と判断力が求められます。そのため、運転者には一般的な交通法規の知識だけでなく「安全な運転」に関する専門的な知識や技能の習得が不可欠です。
この教育は継続的かつ計画的に実施する必要があります。また、教育を行った日や場所、教えた内容、講師と受講者の情報は営業所で3年間保存しなければなりません。
乗務員教育を怠るとどうなる?
運転者への指導・監督、点呼の実施、乗務時間の管理や健康状態の把握など、安全運行を支える「3本柱」は法律で定められた重要な義務です。しかし、これらを守れていない事業者が多く、違反の大半を占めているのが現状です。こうした義務違反は事故につながる重大なリスクをはらんでいるため、国は厳しい行政処分を科しています。
行政処分には、許可の取消や事業停止、車両使用停止(延使用停止日車数)、車両停止1件あたりの日車数、文書警告、文書勧告等があります。
【年間教育】法定13項目(指導監督指針)

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車を安全に運行するため、すべての運転者に対して定められた内容に基づく教育(指導および監督)を実施しなければなりません。「指導監督指針」により13項目の教育内容が明示されており、安全運転の意識向上と事故防止のために不可欠な取り組みです。
1.事業用自動車を運転する際の心構え
旅客自動車運送事業は、公共性の高い輸送事業であり、乗客を安全かつ確実に目的地まで届けることが社会的な責務です。ドライバーにはその使命を自覚させるとともに、事業用自動車による交通事故の統計などを用いて、万が一の事故が社会に及ぼす影響の大きさを具体的に理解させる必要があります。
そのうえで、運行の安全の徹底、乗客の命と安心を守ること、交通社会全体の模範となるような運転を実践することが、プロドライバーとしての使命であることをしっかりと認識させなければなりません。
2.事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
ドライバーには、道路運送法・道路交通法・道路運送車両法に基づいて定められた遵守事項(運行指示書の内容を含む)を正しく理解させることが必要です。あわせて、これらのルールを無視した運転や、日常点検を怠ったことで発生した交通事故の事例を紹介し、そうした行為が重大な事故につながることを具体的に示すことが重要となります。
さらに、事故を起こした事業者や運転者に対する行政処分の内容や、事故が加害者・被害者・その家族など関係者に与える精神的・社会的影響を説明することで、法令遵守の重要性と責任の重さを深く理解させることが求められます。
3.事業用自動車の構造上の特性
ドライバーには、自分が運転する事業用自動車の「車高」「視野」「死角」「内輪差」「制動距離」などの特徴をしっかりと確認させ、これらの特性が車両によって異なることを理解させる必要があります。また、こうした車両特性を正しく把握していなかったことによって発生した交通事故の事例を紹介することで、事業用自動車の構造上の特性を事前に把握する重要性を認識させなければなりません。
さらに、これまで乗務していた車両と制動装置や変速装置の操作感が大きく異なる車両に乗務する場合には、事前にその操作性を十分に確認させるなど、安全な運行に向けた準備を徹底させましょう。
4.乗車中の旅客の安全を確保するために留意すべき事項
急発進や急ブレーキ、急ハンドルといった操作が原因で、旅客が車内で転倒した事故の事例を紹介し、こうした急な操作は極力避けるべきであることを理解させます。
あわせて、走行中に旅客が立ち上がらないよう促すことや、シートベルトが備わっている座席では必ず着用させるなど、乗車中の旅客の安全を守るために必要な注意事項を指導します。
5.旅客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項
乗降用ドアの誤操作によって旅客がドアに挟まれるなどの事故が発生した事例を紹介しながら、乗降時には旅客の動きを十分に確認し、扉の開閉装置を正しく扱うことの重要性を理解させます。
6.運行路線・経路における道路及び交通の状況
運行する路線や経路に関する道路工事の有無、交通規制、天候の変化、所要時間の目安などの最新情報を事前に把握しておくことの重要性を運転者にしっかり理解させましょう。あわせて、過去にヒヤリとした事例があった危険箇所などについても、事前に確認し、安全運転への意識を高めることが必要です。
7.危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
強風や豪雪などの悪天候は、運転にさまざまな影響を与える恐れがあります。急な加速・ブレーキ・ハンドル操作によって、乗客が転倒することにもつながります。乗降扉の誤操作による挟まれ事故や右左折時の内輪差、車両のすぐ近く(前・後ろ・左側)の死角など、貸切バスの運転には多くのリスクが潜んでいることを改めて理解しなければなりません。
また、乗客の呼び止めや乗車希望に反応して、急な進路変更や急停止を行った場合にも事故のリスクが高まります。これらの危険を正しく理解した上で未然に防ぐためには、危険予知トレーニングを活用しながら、事故につながる要因を予測・回避する力を養うことが重要です。あわせて「指差呼称」や「安全呼称」など、自ら注意を促す行動を習慣化することで、より確実な安全運転ができるでしょう。
さらに、緊急時のブレーキ操作などの技術を維持するために、実際の業務車両と同じタイプの車を使って急ブレーキの操作訓練も実施します。事故や災害など緊急時の対応方法についても、具体的な事例をもとに理解を深めるような指導も必要です。
8.運転者の運転適性に応じた安全運転
適性診断などを通じて、運転者一人ひとりの運転のくせや傾向を把握し、自分自身の運転スタイルを客観的に理解してもらいます。また、ストレスや体調といった心身のコンディションにも目を向け、状況に応じた適切なアドバイスや指導を行います。
9.交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法
長時間にわたる連続運転や睡眠不足、薬の服用による眠気や飲酒による体調変化など、生理的な原因によって集中力が低下し事故を引き起こすおそれがあることを、実際の事例を用いて運転者に理解させましょう。また「慣れ」や「自分の運転技術への過信」といった心理的な油断も、注意力の低下につながることをしっかり認識させる必要があります。
あわせて、運輸規則第21条第1項および国土交通省告示(平成13年告示第1675号)で定められた、運転者の勤務時間・乗務時間の基準についても確実に理解させましょう。さらに、運転中に疲れや眠気を感じた場合には、速やかに運転を中止して休憩や仮眠を取るよう指導するとともに、飲酒運転や薬物の使用については厳しく禁止し、再発防止の意識を徹底させることが重要です。
10.健康管理の重要性
疾病が交通事故を引き起こす要因となる可能性があることについて、具体的な事例を挙げて運転者に理解を促すとともに、定期的な健康診断や心理的負担の把握を目的とした検査の結果に基づいて生活習慣の改善を図り、心身の健康を適切に管理することの重要性を理解させることが求められます。
11.安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法
安全運転支援装置などを備えた事業用自動車を運行する際には、その機能に過度な信頼を寄せたり、誤った使い方をしたりすることで、かえって事故につながる可能性があることを運転者に説明しましょう。こうしたリスクを正しく理解させたうえで、機器に頼りすぎることなく、正しい使い方と安全運転の基本を守るよう指導することが重要です。
12.ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転
運転者からヒヤリ・ハットの体験報告があった場合や、貸切バスの運転に関する苦情が寄せられた場合、あるいは事故が発生した際には、ドライブレコーダーの映像を活用し、加速・ブレーキ・ハンドル操作が急でなかったか、車間距離の確保や交通法規の遵守がなされていたかを確認します。
そのうえで、運転者に自身の運転傾向を理解させ、必要に応じて具体的な指導を実施します。
13.ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリ・ハット体験等の自社内での共有
ドライブレコーダーの映像のうち、「12.ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転」に該当する事例については、記録された内容を当該運転者本人だけでなく、他の運転者への指導や教育にも活用することで、より実効性のある指導・監督が可能になります。実際の映像をもとに危険場面や改善点を共有することで、全体の安全意識と運転技術の向上につながります。
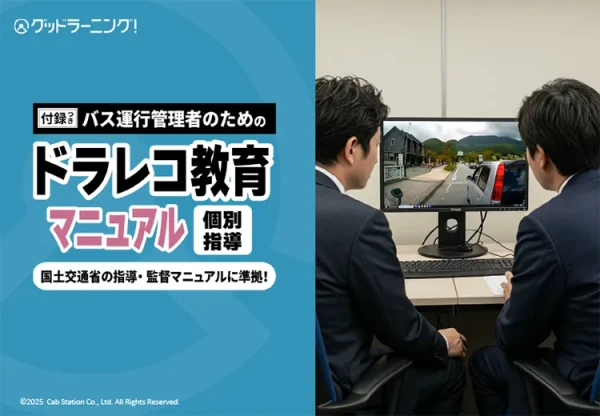
年間教育計画表・乗務員教育記録簿の作成と保存も義務
運転者への年間教育は、指導記録簿を作成して3年間保存が必要です。指導記録簿の作成にあたっては、以下の事項が必須となります。
- 実施日時
- 実施場所
- 実施内容
- 指導・監督を行った者及び指導・監督を受けた者の氏名
特定の運転者に対する特別な指導
旅客自動車運送事業者は、道路運送法に基づく運輸規則の定めにより、運転者に対して日常的な指導や監督を行うだけでなく、特定の条件に当てはまる運転者に対しては、より丁寧で特別な指導を行うことが義務づけられています。
事業者は運転者一人ひとりの状況を踏まえて、適切なタイミングで十分な時間を確保し、安全運行のために必要な内容をしっかりと確認・指導しなければなりません。
初任運転者・準初任運転者
ここでいう初任運転者と準初任運転者は、以下を指します。
初任運転者:次のいずれかに掲げる者(貸切バス以外の一般旅客自動車の運転者として新たに雇い入れた者又は選任した者にあっては、雇い入れの日又は選任される日前 3 年間に他の旅客自動車運送事業者において当該旅客自動車運送事業者と同一の種類の事業の事業用自動車の運転者として選任されたことがない者に限り、特定旅客自動車の運転者として新たに雇い入れた者又は選任した者にあっては、過去3年間に乗合バス、貸切バス、ハイヤー・タクシー及び特定旅客自動車のいずれの運転者としても選任されたことがない者に限る。)
①当該旅客自動車運送事業者において事業用自動車の運転者として新たに雇い入れた者
②当該旅客自動車運送事業者において他の種類の事業用自動車の運転者として選任されたことがある者であって当該種類の事業の事業用自動車の運転者として初めて選任される者
準初任運転者:初任運転者以外の者であって、直近1年間に当該一般貸切旅客自動車運送事業者において運転の経験(実技の指導を受けた経験を含む。)のある貸切バスより大型の車種区分の貸切バスに乗務しようとする運転者
出典:旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
初任運転者に対する特別な指導は以下の内容です。
■初任運転者に対する特別な指導の内容
①事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項
道路運送法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項及び交通ルール等(貸切バスの運転者にあっては、運行指示書の遵守を含む。)を理解させるとともに、事業用自動車を安全に運転するための基本的な心構えを習得させる。
②事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法
事業用自動車の基本的な構造及び装置の概要及び乗合バス又は貸切バス等の運転者にあっては車高、視野、死角及び内輪差等の他の車両との差異を理解させるとともに、日常点検の方法を指導する。この場合において、貸切バスの運転者にあっては、当該運転者が実際に運転する事業用自動車と同一の車種区分の自動車を用いて指導する。
③運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項
旅客自動車運送事業者の事業の態様及び運転者の乗務の状況等に応じて、シートベルトの着用を徹底させることその他の事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項を指導する。
④危険の予測及び回避
道路、交通及び旅客の状況の中に含まれる交通事故につながるおそれのある主な危険を理解させるとともに、それを回避するための運転方法等を指導する。また、貸切バスの運転者にあっては、当該運転者が実際に運転する事業用自動車と同一の車種区分の自動車を用いて、制動装置の急な操作の方法について指導する。
⑤安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法
安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスを運転する場合においては、当該装置の機能への過信及び誤った使用方法が交通事故の要因となった事例を説明すること等により、当該貸切バスの適切な運転方法を理解させる。
⑥ドライブレコーダーの記録を利用した運転特性の把握と是正
貸切バスの運転者にあっては、⑦の安全運転の実技を実施した時のドライブレコーダーの記録により運転者に自身の運転特性を把握させた上で、必要に応じて是正のために必要な指導を行う。
⑦安全運転の実技
実際に運行する可能性のある経路(高速道路、坂道、隘路、市街地等)において、道路、交通及び旅客の状況並びに時間帯を踏まえ、当該運転者が実際に運転する事業用自動車と同一の車種区分の自動車を運転させ、安全な運転方法を添乗等(貸切バスの運転者にあっては、添乗)により指導する。
貸切バス以外の一般旅客自動車及び特定旅客自動車の運転者に対しては、①から④までに
ついて合計 6 時間以上実施すること。⑦については、可能な限り実施することが望ましい。貸切バスの運転者に対しては、①から⑥までについて合計 10時間以上、⑦について 20 時間以上実施すること。
出典:旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
準初任者運転者については、上記に規定する特別な指導の内容のうち、少なくとも④(制動装置の急な操作に関する内容に限る。)、⑥及び⑦について実施します。実施時間は、⑦について 20 時間以上、その他については当該一般貸切旅客自動車運送事業者において同様の内容を初任運転者に対して実施する時間と同程度以上の時間が必要です。
初任運転者は、当該旅客自動車運送事業者において初めて当該事業の事業用自動車の運転者に選任される前に特別な指導を実施しなければなりません。また、準初任運転者は直近1年間に当該一般貸切旅客自動車運送事業者において運転の経験(実技の指導を受けた経験
を含む。)のある貸切バスより大型の車種区分の貸切バスに乗務する前に、特別な指導を実施しなければなりません。
事故惹起運転者
事故惹起運転者とは、死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こした運転者及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者を指します。
事故惹起者に対する特別な指導は以下の内容です。
■事故惹起運転者に対する特別な指導の内容
①事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全の確保に関する法令等
事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するため道路運送法その他の法令等に基づき運転者が遵守すべき事項(貸切バスの運転者にあっては、運行指示書の遵守を含む。)を再確認させる。
②交通事故の事例の分析に基づく再発防止対策
交通事故の事例の分析を行い、その要因となった運転行動上の問題点を把握させるとともに、事故の再発を防止するために必要な事項を理解させる。この場合において、貸切バスの運転者にあっては、交通事故時のドライブレコーダーの記録を利用して指導する。
③交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法
交通事故を引き起こすおそれのある運転者の生理的及び心理的要因を理解させるとともに、これらの要因が事故につながらないようにするための対処方法を指導する。
④運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項
旅客自動車運送事業者の事業の態様及び運転者の乗務の状況等に応じて、シートベルトの着用を徹底させることその他の事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項を指導する。
⑤危険の予測及び回避
危険予知訓練の手法等を用いて、道路、交通及び旅客の状況に応じて交通事故につながるおそれのある危険を予測させ、それを回避するための運転方法等を運転者が自ら考えるよう指導する。また、貸切バスの運転者にあっては、当該運転者が実際に運転する事業用自動車と同一の車種区分の自動車を用いて、制動装置の急な操作の方法について指導する。
⑥ドライブレコーダーの記録を利用した運転特性の把握と是正
貸切バスの運転者にあっては、⑦の安全運転の実技を実施した時のドライブレコーダーの記録により運転者に自身の運転特性を把握させた上で、是正のために必要な指導を行う。
⑦安全運転の実技
実際に運行する可能性のある経路(高速道路、坂道、隘路、市街地等)において、道路、交通及び旅客の状況並びに時間帯を踏まえ、当該運転者が実際に運転する事業用自動車と同一の車種区分の自動車を運転させ、安全な運転方法を添乗等(貸切バスの運転者にあっては、添乗)により指導する。
貸切バス以外の一般貸切旅客自動車運送事業の事業用自動車(以下「一般旅客自動車」と
いう。)及び特定旅客自動車の運転者に対しては、①から⑤までについて合計 6 時間以上実施すること。⑦については、可能な限り実施することが望ましい。貸切バスの運転者に対しては、①から⑥までについて合計 10時間以上、⑦について 20 時間以上実施すること。
出典:旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
事故惹起運転者は、当該交通事故を引き起こした後再度事業用自動車に乗務する前に特別な指導を実施します。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りではありません。
高齢運転者
高齢運転者には、適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導しなければなりません。なお、特別な指導は適性診断の結果が判明した後1か月以内に行う必要があります。
貸切バス乗務員の教育方法は何がある?

貸切バス乗務員の教育方法には、座学や実技研修、e-ラーニングなどがあります。
座学は講師が直接指導するスタイルで、安全運転や法令などを学びます。グループでのディスカッションや質疑応答では、能動的な学習ができるのも特徴です。講師の経験やノウハウを直接学べ、参加者同士の意見交換も促進されるため理解を深められます。しかし、スケジュールの調整が難しかったり、移動や開催場所のコストがかかってしまうデメリットもあります。
実技研修は、実際の車両を使って安全運転技術や緊急時の対応を体験的に学ぶスタイルです。実践的な技能が身につく上、講師が直接動作チェックをしてくれるので、的確な指導を受けられます。しかし、時間や場所、車両の手配が必要でコストがかかる上、講師がチェックできる人数には限りもあるため、参加人数に制限がある場合も多いです。
そしてe-ラーニングの特徴は、パソコンやスマホ、タブレットでいつでもどこでも学習できることです。動画やアニメーションを多用しているため、視覚的に理解しやすくなっています。反復学習ができ、理解度のテストも簡単に受けられる上、管理者は受講状況やテスト結果を一元管理できるので人件費もあまりかかりません。なお、利用にはネット環境や端末が必要です。
貸切バスの乗務員教育はグッドラーニング!

グッドラーニング!は、貸切バス事業者向けに特化したeラーニング型の安全教育サービスです。国土交通省の指導監督指針に対応しており、乗務員の自主的な学びを促しながら、管理者の業務負担も大幅に軽減します。
ここでは、貸切バスの乗務員教育にグッドラーニング!が選ばれる3つの理由をご紹介します。
eラーニングなのでパソコン、スマホで学習可能
グッドラーニング!はインターネット環境があれば、パソコンやスマホ、タブレットからいつでもどこでも受講可能です。移動時間や休憩時間などの隙間時間を活用できるため、忙しい乗務員でも無理なく自分のペースで安全教育を進められます。また、一度学習した内容は何度でも繰り返し視聴できるため、理解度を深めるのにも役立ちます。
国土交通省指定の安全教育に対応
グッドラーニング!は指導監督の各項目のバス13項目に対応しています。安全講座は直近の法令改正に対応した最新版を自動配信しており、毎年教材内容をリニューアルしているので、マンネリ化を防ぐだけではなく飽きずに楽しく学習ができます。国土交通省指定の安全教育に対応しており、2024年の実績では契約の継続率は97%です。
監査に必要教育記録簿などがワンクリック出力
グッドラーニング!は管理者用の機能も充実しています。管理画面は一目で分かる使いやすさで、受講者ごとの受講履歴やテスト結果が自動的に集計される仕組みなのです。そのため、監査に必要な指導教育記録簿もワンクリックで簡単に作成・出力できます。
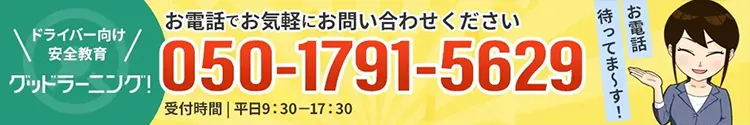
まとめ

貸切バスの安全運行を支える乗務員教育は、単なる法的義務を超え、事故防止や利用者の信頼を守るための不可欠な取り組みです。法定13項目をはじめとした体系的かつ計画的な教育を継続的に実施することで、運転者一人ひとりの安全意識や運転技術を着実に向上させられます。
日常の業務においても高い安全基準を維持し、安心して利用できる運行体制の確立へとつなげましょう。事業者としては、この教育を通じて安全文化を根付かせ、社会的責任を果たしていくことが求められています。
当社の記事・お知らせに関する注意事項
- 最新の法改正・制度改正が必ずリアルタイムで記事に反映されているわけではありません。
- 情報を掲載するにあたり、事実と相違がないように注意しておりますが、絶対の正確性をお約束しているわけではありません。
- 掲載された情報の利用により何らかの損害が生じたとしても、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

