Useful Informationお役立ち情報
- ドライバー安全教育のグッドラーニング! ホーム
- お役立ち情報
- 【法定12項目】ドライバー教育用の資料ってどうしたらいい?
【法定12項目】ドライバー教育用の資料ってどうしたらいい?
事業用トラック安全教育
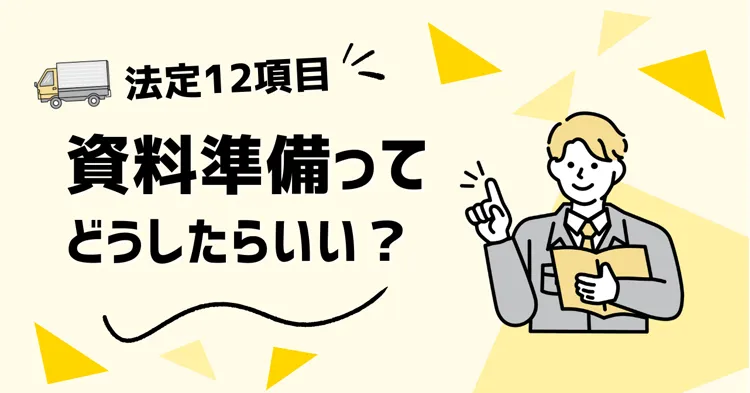
物流の主流となっているトラック輸送では、ドライバーに対して運送業者は安全教育を行わなければなりません。その中で特に重要なのは法定12項目であり、これらの教育をきちんと行っていないと見なされると、行政処分の対象となります。しかし、どのように教育をすれば良いのか、方針が明確になっていない企業も多いでしょう。ここでは法定12項目の概要をお伝えするとともに教育資料に関してどのようなものがあるか紹介します。
そもそも指導教育を行う目的とは?
法定12項目とは国土交通省が制定した「貨物自動車輸送安全規則」(正式名称:貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針)という法律であり、運送業者はドライバーに対して「安全に配慮し、他の模範となるような運転を意識する」ように教育をしなければならないという法律になります。
したがって、安全に配慮し、事故を起こさないようにするというのが教育を行う目的となります。教育指導では、国土交通省が公表しているドライバーの安全教育の指針である「法定12項目」で紹介します。
「法定12項目」の具体的な内容を解説!

ここでは以下の法定12項目の概要を紹介していきます。
- 事業用自動車を運転する場合の心構え
- 事業用自動車の安全運行を確保するための遵守事項
- 事業用自動車の構造上の特性
- 貨物の正しい積載方法
- 過積載の危険性
- 危険物を運搬する場合に留意すべき事項
- 適切な運行の経路及び当該経路における道路および交通の状況
- 棄権の予測及び回避ならびに緊急時における対応方法
- 運転者の運転適性に応じた安全運転
- 交通事故に関わる運転者の生理的および心理的要因ならびにこれらへの対処方法
- 健康管理の重要性
- 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法
1.事業用自動車を運転する場合の心構え
輸送事業は公共的な事業であり、貨物を安全かつ確実に輸送することが求められることや、事故を起こした場合における社会に与える影響の大きさを、ドライバーに認識させることが輸送事業者に求められます。
例えば、ドライバーが事故を起こした場合には輸送がストップしてしまい輸送先の企業にも迷惑をかけてしまいます。また、事故の報道が起きてしまった場合には自社の経営にも影響が出てしまうでしょう。
2.事業用自動車の安全運行を確保するための遵守事項
自動車運送事業法、道路交通法、道路運送車両法に基づき守るべき事項を理解させる必要があります。また、日常の点検が非常に重要であること、事故を起こした場合の運転者に対する処分、および加害者・被害者とその関係者に与える心理的影響を理解させることが求められます。
3.事業用自動車の構造上の特性
トラックなどの事業用自動車は乗用車に比べて車高や視野、死角、内輪差などが大きく異なります。また、自動車を牽引してコンテナを運搬する場合において、コンテナを確実に固定するなど、安全配慮のポイントも異なります。これらを運転者に理解をさせる必要があります。
4.貨物の正しい積載方法
貨物を積載する際には、偏荷重や運転中の荷崩れが生じないような貨物の積載方法・固縛方法を運転者に指導させる必要があります。また、偏荷重が生じた場合ではカーブを通行した時に遠心力により転倒のリスク、事故のリスクが高くなる事例をあげつつ、教育を行う必要があります。
5.過積載の危険性
過積載に起因する交通事故の事例を説明しながら、過積載の安全性に与える影響および過積載による運行を行ったときの運送事業者、運転者、荷主に対する処分を理解させる必要があります。
6.危険物を運搬する場合に留意すべき事項
危険物に該当する貨物の種類と性質、危険物を運搬する前の確認事項、取り扱い方法、積載方法、運搬方法に関して運転者に理解させる必要があります。また、危険物が飛散したり、漏洩したりした場合にどのように安全確保を行うのか、万が一の事態を考えて、対応すべき方法を指導する必要があります。
7.適切な運行の経路および当該経路における道路および交通の状況
ヒヤリ・ハット体験の事例を説明しつつ、貨物を輸送する際のルートおよび交通状況を事前に把握しておくことの重要性を指導します。また、実際に輸送する際にもあらかじめ設定した経路を通行するように指導をします。
8.危険の予測および回避ならびに緊急時における対応方法
強風や豪雪、豪雨などの悪影響が運転に与える影響や、右折時、左折時の内輪差や死角など危険になりうるポイントに関して危険予知訓練などの手法を用いて教育を行います。また、それらの危険に対して、危険を予測し、事前に回避をするために指差呼称や安全呼称を行う習慣を体得させる必要があります。他に事故発生時、災害発生時の対応方法について事例を交えて理解させる必要があります。
9.運転者の運転適性に応じた安全運転
運転者に自身の運転傾向を理解させるとともに、ストレスや心身の状況を理解させます。またこの運転適性については、定期的に一般適性診断を受診している事業所の診断結果を活用するのも良いでしょう。一般適性診断を活用しない場合は、運転手にどのような癖があるのか把握してもらうよう指導教育するようにしましょう。
10.交通事故に関わる運転者の生理的および心理的要因ならびにこれらへの対処方法
運転者でも長時間運転すると疲れてしまいます。これらの過労や睡眠不足、薬の副作用や飲酒の影響や、自らの運転技能への過信による集中力の欠如による影響について事例をあげて説明し、理解させる必要があります。また、勤務時間や乗務時間を理解させるとともに、運転中に疲労や眠気を感じたときは運転を中止し、休憩・睡眠を取ることを徹底させ、飲酒運転、酒気帯び運転及び覚せい剤等の使用の禁止を徹底させます。
11.健康管理の重要性
疾病が交通事故の要因となるリスクがあることを事例交えて説明するとともに、健康診断の結果や、ストレスチェックの結果等に基づいて生活習慣の改善や心身の健康管理を行うことの重要性を理解させます。
12.安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法
安全性の向上を図るための装置を備えている事業用自動車を運行する場合には、該当装置の使い方および誤った使い方をした場合の危険性を理解させる必要があります。
安全教育・指導を行わないと違反対象になる

安全教育・指導を行わないと違反になります。ここでは行政がどのように確認を行うのか、またどのような違反の事例があるのか以下の2つを紹介いたします。
行政における教育実施状況確認方法
運送業許可を取得し、一般的には運輸開始後、半年以内に実施され、初回の巡回指導でA判定を取得した場合には2~3年での巡回指導となります。
巡回時には指導教育計画表や運転者指導記録簿を確認されることになるので、事前に準備しておきましょう。特に運転者指導記録簿は3年にわたり保存する義務があるので、紛失しないように気を付けましょう。
違反時の対応
違反時には厳しい罰則が下ります。例えば、虚偽記載をした場合や改ざんをした場合には初回であれば60日車の運送施設の使用停止、再違反であれば120日車の運送施設の使用停止処分が下ります。罰則が下ると運送施設や運送会社だけでなく、荷主にも大きな影響を与えてしまうことになるので十分に気を付けるようにしましょう。
法定12項目に対応したドライバーの教育資料ダウンロード先は?

法定12項目の概要をお伝えいたしましたが、これらを全運転者に教育を行うことは大変であり、自前で資料を用意するのも難しいと思います。ここでは公開されている有用な教育資料とそのメリット・デメリットを次の3つからお伝えいたします。
国土交通省のマニュアル
公開されている資料の1つとして国土交通省のマニュアルがあります。トラックのマニュアルの場合、計140ページ近くある大作となっております。国土交通省が作成したマニュアルということでこの1冊ですべてを理解できるようになっております。しかし、その一方で、教科書のような形式となっており、文章量が多く教育資料としては使いにくいです。また、実際に誰に対していつ教育を行ったかという管理に関しては考慮されていないため、管理自体を別の媒体で行わなければならないのもデメリットと言えるでしょう。
ダウンロード先:自動車総合安全情報ホームページ
公益社団法人 全日本トラック協会の資料
全日本トラック協会が公開している資料もあります。しかしこちらの資料は、国土交通省が公開している教育資料と似たような資料になります。
ダウンロード先:公益社団法人全日本トラック協会
eラーニングシステム「グッドラーニング!」を活用してみませんか?

国土交通省が提供している資料の他にグッドラーニング!というクラウド型eラーニングシステムがあります。月額料金がかかってしまうデメリットがありますが、メリットが多々あります。主なメリットは以下の通りです。
- eラーニングでスマホでも受講できるので、ドライバーの積込や荷卸しの待機時間を有効活用できます。
- 最新版の教育資料が常に配信されます。
- チェックテストがあるので、受講者の理解度をチェックできます。
- 自社のドラレコの情報を利用してヒヤリ・ハット状況の共有などオリジナル教材を作ることができます。
- 指導教育記録簿を自動で作成でき、年間教育計画表や指導教育記録簿の出力も容易です。
eラーニングを使わない場合、教育をする人に対する人件費や年間教育計画表・ 指導教育記録簿の作成時間など多くのコストが発生します。これらのコストをほぼ0にできるということで、有料ではあるものの十分な効果が見込めるシステムであると言えるでしょう。無料デモも公開しているので、ぜひ一度確認してみるとよいでしょう。
まとめ
ここでは法定12項目の概要解説と教育資料のメリット・デメリットを解説しました。法定12項目は結構な分量があるにも関わらず毎年実施しなければなりません。事故を可能な限り未然に防ぐことは会社、加害者・被害者およびその関係者、荷主のいずれにしても重要です。 しかし、実施を徹底するのは大変であり、教育者の人件費や年間教育計画表・ 指導教育記録簿の作成時間など多くのコストがかかることになります。また、ドライバーの負担も少なくありません。e-ラーニングを活用することでコストや負担を解決することができる可能性があります。ぜひ活用を検討してみてください。
当社の記事・お知らせに関する注意事項
- 最新の法改正・制度改正が必ずリアルタイムで記事に反映されているわけではありません。
- 情報を掲載するにあたり、事実と相違がないように注意しておりますが、絶対の正確性をお約束しているわけではありません。
- 掲載された情報の利用により何らかの損害が生じたとしても、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

