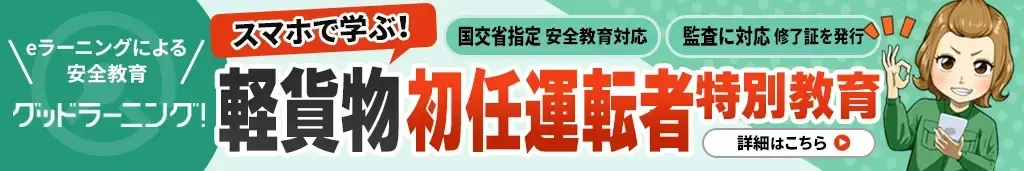Useful Informationお役立ち情報
- ドライバー安全教育のグッドラーニング! ホーム
- お役立ち情報
- 【解説】軽貨物の安全管理者選任はいつから義務化?罰則は?
【解説】軽貨物の安全管理者選任はいつから義務化?罰則は?
軽貨物
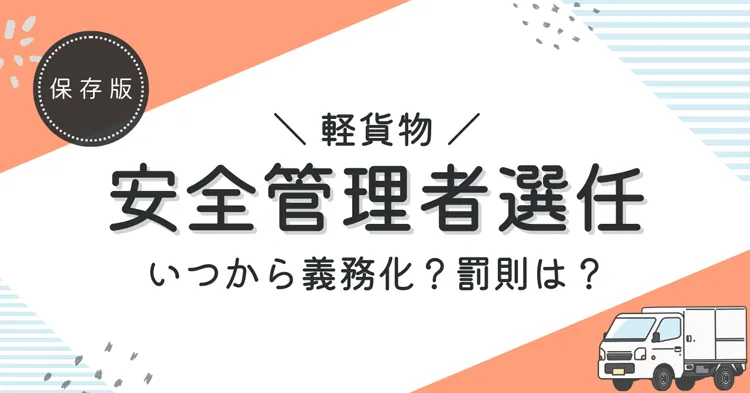
軽貨物の安全管理者選任はいつから義務化された?EC市場の拡大により、宅配便の配達個数が大幅に増えてきています。このような現状から、軽自動車を使った配送が増加し、これを受けて軽貨物自動車運送事業における安全を強化する目的で義務化されたのが、軽貨物の安全管理者選任です。義務化までの道のりや罰則を詳しく見ていきましょう。
- 貨物軽自動車の安全管理者制度はいつから施行される?
- 新制度で義務化された5つの項目
- 貨物軽自動車安全管理者に対する罰則とは
- 運行管理者と安全管理者の違い
- 安全管理者になる方法!なにか資格は必要?
- まとめ
貨物軽自動車の安全管理者制度はいつから施行される?

2025年4月1日から施行される貨物軽自動車の安全管理者制度は、貨物軽自動車運送事業における安全対策強化のために設けられた制度のことです。近年、EC市場の拡大によって宅配便の取り扱い個数が増加しており、荷物を届ける手段の1つとして、軽自動車での運送需要が高まっています。
一方で、保有台数1万台あたりの事業用軽自動車による死亡事故や重要事故の件数が、右肩上がりで増加しているのも事実です。そのため、安全対策を目的として2024年5月15日に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律および貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」が公布されました。その際に貨物自動車運送事業輸送安全規則なども改正されることとなったのです。
| 公布 | 2024年10月1日 |
|---|---|
| 施行 | (1)講習機関にまつわる登録関係:2024年11月1日 (2)貨物軽自動車運送事業者に対する規制関係:2025年4月1日 |
猶予期間はあるのか?
2024年10月1日に公布された貨物軽自動車安全管理者制度は、11月1日から講習機関にまつわる登録が施行されました。新制度は2025年4月1日よりスタート予定です。既存の軽貨物運送事業者に対しては、以下の猶予期間が設けられています。
- 貨物軽自動車安全管理者の選任:施行後2年
- 特定の運転者への特別な指導及び適性診断の受診:施行後3年
猶予期間があるとはいえ、直前になって慌てないよう早めの準備がおすすめです。
新制度で義務化された5つの項目
ここでは新制度で義務化された5つの項目を詳しく見ていきます。なお、ここでの貨物軽自動車運送事業者とは、バイク便事業者を除いた事業者のことです。
(1)貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講
「貨物軽自動車安全管理者」を選任する際は、その人に対して、国土交通大臣の登録を受けた講習機関にて、貨物自動車安全管理者講習を受けさせなければなりません。貨物軽自動車安全管理者は、選任後2年ごとに定期講習を受ける必要があります。
- 貨物軽自動車安全管理者講習:貨物軽自動車安全管理者の選任にあたり受講
- 貨物軽自動車安全管理者定期講習:選任後2年ごとに受講
※貨物軽自動車運送事業以外の貨物自動車運送事業も行っている場合であって、現に運行管理者として選任されている者を除く
また、貨物軽自動車運送業者は、営業所ごとに安全管理者を選任し、定められている項目を運輸支局に届け出なければなりません。安全管理者の選任基準と、届け出る項目は以下の通りです。
■安全管理者の選任基準
次のいずれかに該当する者です。
- 貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者
- 貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前2年以内に修了した者
- 当該事業者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営している場合に、運行管理者として選任されている者
■安全管理者の主な届出項目
- 貨物軽自動車運送事業者の氏名又は名称
- 貨物軽自動車安全管理者の氏名及び生年月日
- 貨物軽自動車安全管理者の選任年月日及び講習修了年月日
安全管理者に選任されたら、講習内容をしっかりと理解し課せられている安全対策を確実に行いましょう。
なお、令和7年3月までに貨物軽自動車運送事業経営届出を行った事業者は、令和9年3月までに選任する必要があります。令和7年4月以降に貨物軽自動車運送事業経営届出を行う事業者は、当該届出後事業を開始する前までに速やかに選任しましょう。
(2)業務記録の作成・保存
貨物軽自動車運送事業者は、行った業務に関して以下の項目の記録を作成し、1年間保存しなければなりません。
■主な記録項目
- 運転者等の氏名
- 車両番号(ナンバープレート等)
- 業務の開始、終了及び休憩の日時
- 業務の開始、終了及び休憩の地点
- 業務に従事した距離
- 主な経過地点
(3)事故記録の作成・保存
事故が発生した場合、貨物軽自動車運送事業者は以下の項目の記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
■主な記録項目
- 乗務員等の氏名
- 事故の発生日時
- 事故の発生場所
- 事故の概要
- 事故の原因
- 再発防止対策
(4)国土交通大臣への事故報告
貨物軽自動車運送事業者は、死傷者を生じる重大な事故が発生した場合、以下の項目について30日以内に、所定の様式で運輸支局等を通じて国土交通大臣に報告しなければなりません。また、2名以上の死者を生じた事項については、24時間以内に運輸支局等に速報する必要があります。
■主な記録項目
- 自動車の使用者の氏名又は名称
- 事故の発生日時
- 事故の発生場所
- 当時の状況
- 当時の処置
- 事故の原因
- 再発防止対策
(5)特定の運転者への指導・監督及び適性診断
貨物軽自動車運送事業者は、該当する以下の対象者に対して特別な指導を行わなければなりません。また、国土交通大臣に認定された適正診断の受講もさせる必要があります。さらに、貨物軽自動車運送事業者は、これらの指導および適正診断の受診状況等を記録した「貨物軽自動車運転者等台帳」を作成し、営業所に備え置かなればなりません。
■対象者
- 初任運転者(過去に一度も特別な指導・適性診断を受けていない者)
- 高齢運転者(65歳以上の者)
- 事故惹起運転者(死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者)
貨物軽自動車安全管理者に対する罰則とは
設置が義務付けられている「貨物軽自動車安全管理者」ですが、以下に該当すると罰則が課せられます。
- 重大な事故を引き起こしたときに、報告せず、又は虚偽の報告をした場合:50 万円以下の過料
- 貨物軽自動車安全管理者を選任する規定に違反した場合:100万円以下の罰金
。
貨物軽自動車安全管理者の選任若しくは解任に係る届出をせず、又は虚偽の届出をし た場合:100万円以下の罰金
なお、今回の規制強化に関する行政処分の具体的な基準については、今後制定する予 定です。
参考:国土交通省
運行管理者と安全管理者の違い

安全管理者と間違われやすいのが、運行管理者です。同じ管理者でも担う役割は異なります。
| 運行管理者 | 安全管理者 | |
|---|---|---|
| 管理対象となる自動車の種類 | 緑ナンバー(貨物軽自動車を除く事業用自動車 | 黒ナンバー(バイク便を除く貨物軽自動車) |
| 資格 | 国家資格 (国土交通大臣が行う運行管理者試験に合格した者) |
特別な資格はなし (国土交通大臣の登録を受けた機関による貨物軽自動車安全管理者講習を修了した者) |
業務内容の違い
【運行管理者】
①選任された運転者以外に運行させない
②休憩・睡眠施設の管理
③乗務割の作成
④酒気帯び状態の運転者に運行させない
⑤運転者の健康状態の把握
⑥長距離や夜間に運転する場合の交替運転者の配置
⑦ 過積載防止について従業員へ指導監督を行う
⑧ 貨物の積載方法について従業員へ指導監督を行う
⑨ 通行禁止、制限等違反の防止について運転者へ指導監督を行う
⑩点呼の実施、記録の保存
⑪運転者の業務記録の作成、保存
⑫運行記録計の管理、保存
⑬運行記録計で記録できない車両を運行させない
⑭事故の記録の作成、保存
⑮運転者への運行指示、運行指示書の作成、保存
⑯運転者等台帳の作成
⑰乗務員への指導監督、記録の保存
⑱特定の運転者への指導、適正診断の受診
⑲異異常気象時の措置
⑳補助者への指導監督
㉑ 運行の安全確保についての従業員へ指導監督を行う
㉒乗務基準の作成、乗務員等への指導監督(特別積合せ貨物運送のみ)
㉓運行の安全確保について助言を行う
㉔ 統括運行管理者は運行管理業務を統括する
【安全管理者】
① 休憩・睡眠施設の管理
② 乗務割の作成
③ 酒気帯び状態の運転者に運行させない
④ 運転者の健康状態の把握
⑤ 過積載防止について運転者へ指導監督を行う
⑥ 貨物の積載方法について運転者へ指導監督を行う
⑦ 点呼の実施、記録の保存
⑧ 運転者の業務記録の作成、保存
⑨ 事故の記録・保存
⑩ 運転者等台帳の作成
⑪ 運転者への指導監督、初任運転者等への指導監督、記録の保存
⑫ 適性診断の受診
⑬ 異常気象時の措置
⑭ 運行の安全確保についての運転者へ指導監督を行う
運行管理者が運行の全般を管理する立場であるのに対し、安全管理者は安全について特に重要な項目を管理する立場と言えるでしょう。
参考:自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル
安全管理者になる方法!なにか資格は必要?
軽貨物の安全管理者になるためには、国土交通省が登録した講習機関で貨物軽自動車安全管理者講習を受講する必要があります。
講習内容は、「自動車運送事業、道路交通等に関する法令」「運行管理の業務に関する
こと」「自動車事故防止に関すること」「修了試問及び補習」から構成されており、
5 時間以上実施しなければなりません。
講習機関は「国土交通省ホームページ」から確認すると良いでしょう。
参考:貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について
まとめ
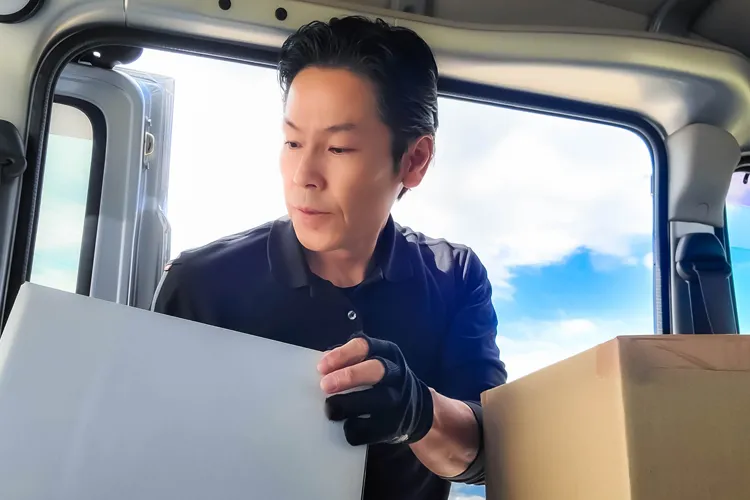
軽EC市場の拡大により、宅配便の配達個数が大幅に増えてきたことから義務化されたのが軽貨物の安全管理者選任です。軽自動車を使った配送が増加し、安全運転に対する意識がますます高まっています。
配達個数が増えると、その分交通事故のリスクも高まります。安全教育に頭を抱える事業者様も多いのではないでしょうか。特に従業員が多い事業者様は、業務の調整や受講状況の管理にも悩まされていることでしょう。そこでおすすめなのがeラーニングです。
時間と場所を選ばずに、全てのドライバー・乗務員に対して効率よく指導教育を実施できます。待機時間を利用しての受講も可能で、クラウド型の教育システムのためタブレットやスマホ、パソコンなどを使って場所を選ばずに受講できます。管理用サイトがあるため、受講者ごとの受講状況やテスト結果も、レポートで確認できるので管理の手間もありません。
ドライバーに対する安全教育を効率よく行いたい事業者様は、ぜひeラーニングをご検討ください。
当社の記事・お知らせに関する注意事項
- 最新の法改正・制度改正が必ずリアルタイムで記事に反映されているわけではありません。
- 情報を掲載するにあたり、事実と相違がないように注意しておりますが、絶対の正確性をお約束しているわけではありません。
- 掲載された情報の利用により何らかの損害が生じたとしても、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。