Useful Informationお役立ち情報
- 【グッドラーニング!】ホーム
- お役立ち情報
- 初任運転者講習とは?対象者・指導内容について解説
初任運転者講習とは?対象者・指導内容について解説
初任運転者講習
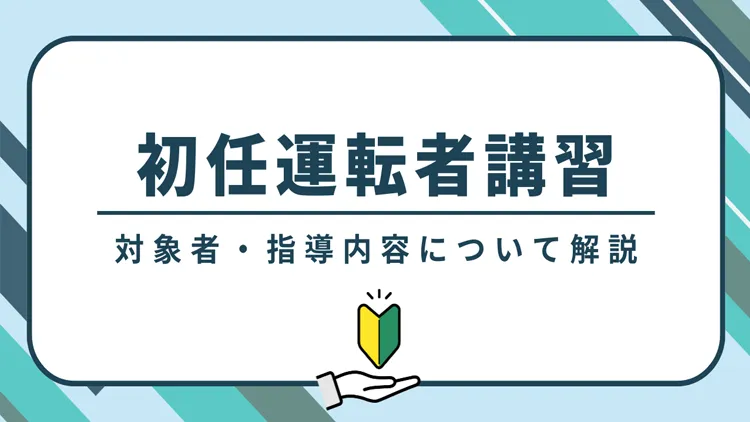
トラック運送会社で運転する際には、「初任運転者講習」を受ける必要があります。 トラックドライバーをはじめるにあたって欠かせない「初任運転者講習」は、内容はもちろん実施期間や研修時間まで事細かに決められているのです。 今回は「初任運転者講習」について詳しくご紹介します。
初任運転者講習とは

「初任運転者講習」とは、国土交通省が運送会社に対して定めている「運転者に対する適切な指導及び監督」の1つである「特定の運転者に対する特別な指導」内の「初任運転者に対する特別な指導」を指します。
大きく分けて「初任運転者講習」と「初任診断」に分けられますが、経験者と未経験者で対応が異なるので注意しましょう。
過去3年以内にトラック運送会社で運転経験がある経験者と、未経験者が対象です。
「初任運転者講習」は国土交通省が定める義務であり、違反すると罰則もあります。
初任運転者講習が免除になる場合
過去3年以内にトラック運送会社(事業用トラック)で運転経験がある方は、初任診断は必須で、「初任運転者講習」は任意となっています。
初任診断については、過去3年以内に初任診断を受診していれば、その診断結果が使用できます。
もし受診していない場合は、しっかりと初任診断を受診しましょう。
過去3年以内にトラック運送会社(事業用トラック)で運転経験がない方は、初任診断と「初任運転者講習」はともに必須で受診が必要です。
つまり「初任運転者講習」が免除になるのは、過去3年以内に事業用の営業車を表す緑ナンバーの運転経験がある方のみです。
初任運転者講習を受けないとどうなる?
もし「初任運転者講習」を受けないとどうなるのでしょうか?
■貨物自動車運送事業に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について
| 違反行為 | 基準日車等 | |
|---|---|---|
| 初違反 | 再違反 | |
| 指導監督告示による運転者に対する指導及び監督違反 | ||
|---|---|---|
| 【1】「2」「3」以外の違反 | ||
| ①一部不適切(指導監督告示の実施状況が2分の1以上である場合) | 警告 | 10日車 |
| ②大部分不適切(指導監督告示の実施状況が2分の1未満である場合) | 10日車 | 20日車 |
| 【2】最高速度違反行為(下命又は容認にまつわるものをのぞく)があったものに限る | 初回警告 | 2回目10日車 3回目20日車 |
| 【3】駐停車違反(駐停車禁止場所および駐車禁止場所による違反をいう)放置駐車違反(自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をいう)その他の道路交通法の違反行為 | 初回警告 | 2回目以上10日車 |
| 指導監督告示による運転者に対する特別な指導および運転適性診断受診義務違反 | ||
|---|---|---|
| 【1】特別な指導の実施状況 | ||
| ①一部不適切(指導監督告示の実施状況が2分の1以上である場合) | 警告 | 10日車 |
| ②大部分不適切(指導監督告示の実施状況が2分の1未満である場合) | 10日車 | 20日車 |
| 【2】運転適性診断の受診状況 | ||
|---|---|---|
| ①受診なし 1名 | 警告 | 10日車 |
| ②受診なし 2名以上 | 10日車 | 20日車 |
| 疾病・疲労等のおそれのある乗務 | ||
|---|---|---|
| 健康診断未受診者 1名 | 警告 | 10日車 |
| 健康診断未受診者 2名 | 20日車 | 40日車 |
| 健康診断未受診者 3名以上 | 40日車 | 80日車 |
「初任運転者講習」を受けなかった本人だけではなく、トラック事業者も指導・監督の責任から処罰の対象となるので、講習は必ず受けるようにしましょう。
初任運転者講習の内容
ここでは、初任運転者に必要不可欠な「初任運転者講習」における12項目の内容をご紹介します。
- 事業用自動車を運転する場合の心構え
- 事業用自動車の安全運行を確保するための遵守事項
- 事業用自動車の構造上の特性
- 貨物の正しい積載方法
- 過積載の危険性
- 危険物を運搬する場合に留意すべき事項
- 適切な運行の経路および当該経路における道路および交通の状況
- 危険の予測および回避ならびに緊急時における対応方法
- 運転者の運転適性に応じた安全運転
- 交通事故に関わる運転者の生理的および心理的要因ならびにこれらへの対処方法
- 健康管理の重要性
- 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法
どれも大切な項目なので、1つでも抜けがないよう指導・教育を行いましょう。
初任運転者(対象者)
初任者運転者の対象となるのは、運転者として新たに雇い入れた者、新たに運転者として従事する者です。
一般貨物自動車運送事業者・トラック事業者の中でも、過去3年以内にトラック運送会社・事業用トラックでの運転経験がない場合は、必ず「初任運転者講習」を受けなければなりません。
その際、白ナンバー経験は該当しないため注意しましょう。
研修の実施時期
「初任運転者講習」は、当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に実施します。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内に実施することも可能です。
1か月を過ぎてしまうと違反の対象となるため、しっかりと計画性を持って取り組む必要があります。
指導内容と研修時間
「初任運転者講習」は、座学や実車を使用して行われます。
改正された指導・監督指針12項目の指導を15時間以上行うほか、実際に事業者トラックを運転させ、安全な運転方法の指導を実施しましょう。
座学と実車、合計35時間以上を実施・教育し、初めて講習が完了します。
座学では「初任運転者に対する特別な指導」に規定されている12項目の内容を学習しますが、教育・指導する12項目の内容はこちらです。
- 事業用自動車を運転する場合の心構え
- 事業用自動車の安全運行を確保するための遵守事項
- 事業用自動車の構造上の特性
- 貨物の正しい積載方法
- 過積載の危険性
- 危険物を運搬する場合に留意すべき事項
- 適切な運行の経路および当該経路における道路および交通の状況
- 危険の予測および回避ならびに緊急時における対応方法
- 運転者の運転適性に応じた安全運転
- 交通事故に関わる運転者の生理的および心理的要因ならびにこれらへの対処方法
- 健康管理の重要性
そのほか、トラックを使用し、日常点検・トラックの構造上の特性について学ばせます。
実技では、講習の対象者にトラックを運転させ、安全な運転方法の指導を行います。
トラック運送会社ごとに、運転者台帳等に記録し保存しておく必要があるので、毎回の内容をしっかりと理解しておきましょう。
実施場所と料金
「初任運転者講習」は、各都道府県のトラック協会やトラック協会指定のドライビングスクール、自社教育で実施可能です。
それぞれ内容はほとんど変わりませんが、料金や時間・手間などに違いがあるため、自社に一番合っている方法で実施しましょう。
■各都道府県のトラック協会の場合(例:東京都トラック協会)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 12項目を6時間実施 ※残り9時間の座学と20時間の実技必須 |
無料 |
■トラック協会指定のドライビングスクール(例:ドライビングアカデミー ODAWARA)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| ①12項目を10時間実施 ※残り5時間の座学と20時間の実技必須 |
32,000円 |
| ②12項目を16時間実施 ※20時間の実技必須 |
50,000円 |
| ③12項目を19時間実施 ※20時間の実施必須 |
72,600円 |
| ④実技を20時間実施 ※15時間の座学必須 |
72,600円 |
また、コストパフォーマンス重視で「初任運転者講習」を行いたいという事業者は、自社教育がおすすめです。
国土交通省の指導監督指針に準拠したe-ラーニングシステム「グッドラーニング!」では、基本の初任運転者講習のほか、改善基準告示の特別講座、ドライブレコーダーの映像を使用した危険予測講座も受けられます。
場所や受講時間を選ばなくて良いので、事業者・受講者ともに手間や負担がありません。
特に事業者自動車の場合、配車業務が忙しくてドライバー教育まで手が回らなかったり、研究にかかるコストの負担が大きかったりと、事業者の悩みが尽きないことでしょう。
そのような時こそ、「グッドラーニング!」のようなe-ラーニングでの指導・教育を活用しましょう。
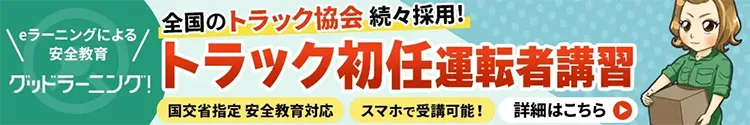
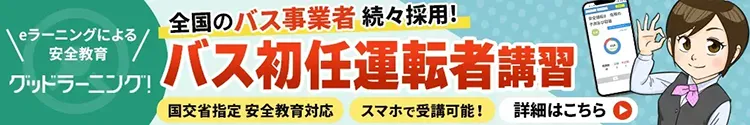
初任運転者教育記録簿
「初任運転者講習」の指導・教育を行った後は、初任運転者教育記録簿にて、実施内容を記録する必要があります。
初任運転者教育記録簿は、必ず記録の詳細を作成し、指導・教育で使用した資料と一緒に保存しましょう。
実施日に参加できなかった運転者は、必ず後日実施します。
その日時等の記録も必ず保存しましょう。
教育に関する記録の保存期間は3年と定められています。
作成にはエクセルやPDFを使用しますが、形式に特に決まりはないので、事業者が管理しやすい形式で問題ありません。
初任診断
「初任運転者講習」において重要になってくるのが、初任診断です。
「貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第22号)」の改正にともない、平成13年9月1日より、貨物自動車運送事業者等は一部の運転者に適性診断をうけさせなければならないことになりました。
これは、初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもので、ドライバーを新たに雇い入れた事業者は、就業者が初めて事業用自動車に乗務する前に初任診断を受診させる義務があります。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内に受診させることも可能です。
ただ、初任診断には3年間の有効期限があるため、過去3年以内に初任診断を受診している場合は、受診が免除になる場合があります。
対象者
「初任診断」は、未経験者・経験者に関係なく、初任運転者すべてが対象です。
初任診断の結果を基に、事故を未然に防ぐための運転行動など、安全運転のための留意点等についての助言・指導を行うため、運送業に従事している人には必須と言えます。
診断の時間と内容
「初任診断」は、1時間40分ほどで終了します。
動作の正確さをはじめ、注意の配分・視覚機能・危険感受性などを診断し、その診断結果をもとに、専任のカウンセラーがカウンセリングを行います。
運転者としての自覚があるか、事故を未然に防ぐためにはどうすればよいかなどの指導・アドバイスを受けるのです。
まとめ
トラック運送会社で運転する際には欠かせない「初任運転者講習」。
座学と実技で35時間以上学ぶ必要があるため、まとまった時間や場所・指導者の確保が必要になってきます。
1つでも項目が抜けてしまうと違反の対象となってしまうため「グッドラーニング!」のようなe-ラーニングシステムを使いながら、効率よく指導・教育していきましょう。
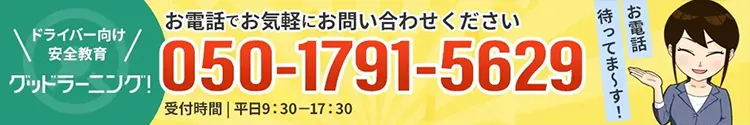
当社の記事・お知らせに関する注意事項
- 最新の法改正・制度改正が必ずリアルタイムで記事に反映されているわけではありません。
- 情報を掲載するにあたり、事実と相違がないように注意しておりますが、絶対の正確性をお約束しているわけではありません。
- 掲載された情報の利用により何らかの損害が生じたとしても、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

