Useful Informationお役立ち情報
- 【グッドラーニング!】ホーム
- お役立ち情報
- セーフティバスの審査内容が変更に!2025年版・知っておくべきポイントを解説(貸切バス事業者安全性評価認定制度)
セーフティバスの審査内容が変更に!2025年版・知っておくべきポイントを解説(貸切バス事業者安全性評価認定制度)
バス安全教育
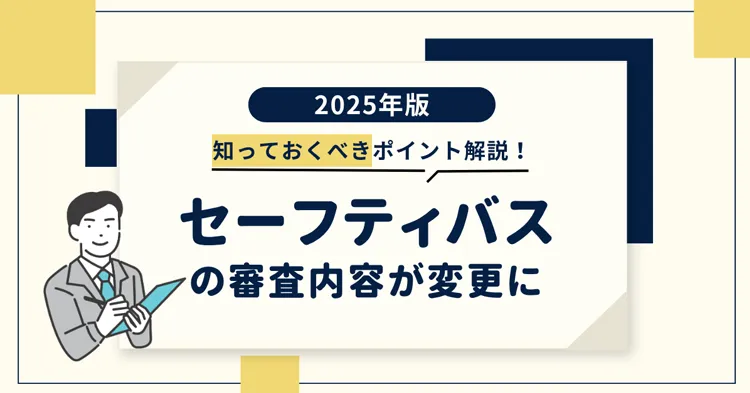
セーフティバスの審査内容が変更に!2025年版・知っておくべきポイントを解説!2025年度からセーフティバスの審査基準が大幅に変更されます。配点構成の見直しや行政処分への減点強化、ASVや健康管理対策の加点など、安全性評価がより重視された新制度に対応するためのポイントを解説します。
セーフティバスの審査内容が変更された背景

「今年も同じ対応で大丈夫」と思っていませんか?実は2024年からセーフティバス制度の審査内容が大きく変わりました。近年、バス業界全体に「安全」と「信頼される運行体制」が求められています。安全対策は形だけではなく、中身や継続性の重視が大切です。
今こそ評価基準変更の経緯や目的を正しく理解しましょう。
制度見直しの経緯と目的
そもそも貸切バスの安全性が考えられるようになったのは、2007年に大阪府・吹田市で起きた「吹田スキーバス事故」が発端でした。この事故は、貸切バスの運転手が、法律で定められた労働時間を上回る過労状態だったことが後の調査で明らかになりました。その後貸切バスに関する安全等対策検討会が開催され、貸切バスの安全性を図ろうと「貸切バス事業者安全性評価認定制度」が確立され、安全確保の取り組みを強化したセーフティバスという仕組みが生まれたのです。
2019年末から猛威を振るったコロナ禍を経て、貸切バスの需要が徐々に回復してきました。それに伴い一層の運行管理強化が必要となり、人為的ミスや健康起因による貸切バスの事故防止が求められています。審査内容の変更は、新たな貸切バス事業者安全性評価認定制度を導入することにより、安全性の向上の促進と貸切バスの信頼を高める目的があります。
事故削減や法令遵守強化への取り組み
記憶に新しい2022年10月に起きた静岡県小山町で起きたバス横転事故では、運転手が乗り心地を重視した結果フットブレーキを多用した結果、ブレーキが利かなくなる「フェード現象」が起きてしまったことと、運行会社や運行管理者も運転手による自己流の運転を把握できておらず、危険性を理解させなかったことが事故の原因と結論づけられました。
事故削減と法令遵守強化への取り組みは、重大事故増加への危機感と、利用者が安心できる安全水準の確保に欠かせません。
事故削減に向けては、ドライバー異常時対応システムなどの先進安全自動車機能導入の評価や「心疾患」「大血管疾患」「視野障害」への検査体制も評価対象に追加されました。また、雪山・山道など危険路での実地訓練を実施する事業者を高く評価することとなりました。
法令遵守強化については、行政処分に対する減点の強化や、法令遵守の配点の廃止、守れていない場合は不認定にするなどの厳しい評価基準となりました。また、評価基準については実効性あるマネジメントを重視した内容に変更されています。
参考:静岡のバス横転事故「フットブレーキ多用」 事故調査委が報告書
変更されたセーフティバス審査内容のポイント
まず、2024年度申請より変更されたのは行政処分の状況による減点強化です。
- 「事故及び行政処分の状況」における行政処分の配点10点について
- 1営業所1回当たり30日車以上50日車以下の行政処分等(警告を含む)を受けた一ツ星事業者の減点方法について
2025年度申請からは、新たな基準で審査・評価されます。主な変更点は以下です。
- 安全性に対する取組状況における配点
- 規則改正への対応
- 先進安全自動車(ASV)の導入に対する加点
- 健康管理に対する加点
- 運輸安全マネジメント取組状況における配点の変更
- 危険度の高い運転に特化した技術向上に対する加点
参考:貸切バス事業者安全性評価認定制度審査内容の変更について
参考:評価項目及び配点変更一覧
参考:配点の変更
最高評価を三ツ星から五ツ星に変更

出典:新たな認定種別(五ツ星)
今回の変更により、三ツ星の3段階における評価から五ツ星の5段階における評価へと変更されました。そのため、昇格は段階的となり、例えば一ツ星認定事業者が80点を取得しても三ツ星とはならず、二ツ星への昇格となります。また、四ツ星で95点以上得点した場合に初めて五ツ星に昇格します。
| 五ツ星認定=95点以上 | ||
|---|---|---|
| 新規 | 60点〜 | ★ |
| 更新① | 70点〜 | ★★ |
| 更新② | 80点〜 | ★★★ |
| 更新③ | 90点〜 | ★★★★ |
| 更新④ | 95点〜 | ★★★★★ |
さらに、2年更新のみとなり、4年更新は廃止されました。4年更新事業者に対する移行措置として、4年更新事業者は通常の2年更新としての申請は認められているものの、更新できなかった場合は申請年度の年度末で有効期間満了となりますので、ご注意ください。2年更新として申請しない事業者は4年更新として扱われます。
例)2023年度認定事業者⇨2025年度に更新申請可
2024年度認定事業者⇨2026年度に更新申請可
配点基準の変更①法令遵守(配点20点→0点)
これまで評価項目にあった「法令遵守(20点)」は廃止されました。その代わり、この20点分の配点は「安全性に対する取り組み(上位事項)(15点)」「運輸安全マネジメントの取り組み(5点)」に振り分けられます。これにより、安全対策やマネジメント体制は、より実際の中身が重視されるようになりました。また、法令を守っていない場合は配点がゼロになるだけではなく審査自体がストップし、不認定となります。
つまり、法令遵守は当たり前であり、加点の対象ではなく資格要件となったのです。
変更前安全性に対する取り組み(法令遵守)20点加点
→20点の加点を廃止
※法令遵守に違反が認められた場合は審査しない。
配点基準の変更②安全性に対する取組状況(上位事項)(配点40点→55点)
新たに追加されたのはASV(先進安全自動車)導入への評価拡張項目です。従来は衝突被害軽減ブレーキのみが対象でしたが、ドライバー異常時対応システム等も加点対象となります。健康管理項目では、睡眠時無呼吸症候群や脳血管疾患対応に加え、心臓疾患・大血管疾患・視野障害への対応も対象になり、運転者の健康リスク対策がより重視されることとなりました。
配点が増えた項目には、衝突被害軽減ブレーキ装置の導入と装着率や適正診断の受診状況、全従業員への教育状況などがあります。以下で詳しく見ていきましょう。
【運行管理等】
・拘束時間、休息期間、運転時間、連続運転時間について、「改善基準告示」よりも厳しい社内基準を設定しているか。(1点)
拘束時間、休息期間、運転時間、連続運転時間について、「改善基準告示」よりも厳しく設定した社内基準を遵守しているか。(2点)
→統合され、
・拘束時間、休息期間、運転時間、連続運転時間について、「改善基準告示」よりも厳しい社内基準を設定し遵守しているか。(2点)
※勤務実績一覧に改善基準告示違反がある場合は評価しない
・対面点呼において、高性能タイプのアルコール検知器を導入し先進的な点呼を行っているか。(1点→2点)
※測定結果が数値で表示されない等の簡易型のアルコール検知器を使用している場合は評価しない。(非対面点呼時も同様)
・衝突被害軽減ブレーキを導入し装着しているか。(3点→4点)
総車両数のうち
①装着率 2割未満の場合 0点
②装着率 2割以上5割未満の場合 2点
③装着率 5割以上の場合 4点
・衝突被害軽減ブレーキ以外のASV装置を導入しているか。※提出単位:事業者(新設:4点)
次の対象装置のうち1両につき2種類以上の装置を装着した車両割合に応じて加点
・ふらつき注意喚起装置
・車線逸脱警報装置
・車線維持支援制御装置
・車両安定性制御装置
・ドライバー異常時対応システム
・先進ライト
・側方衝突警報装置
・統合制御型可変式速度超過抑制装置
・アルコール・インターロック
・事故自動警報システム
総車両数のうち
①装着率 2割未満の場合 0点
②装着率 2割以上5割未満の場合 2点
③装着率 5割以上の場合 4点
・国土交通大臣が認定する「適齢診断」を65歳以上75歳未満の全運転者に対し2年に1回以上受診させているか。※提出単位:事業者(1点→2点)
①2年に1回受診 1点
②毎年受診 2点
【労基法等】
・全従業員に対し、1年に1回以上2年連続で労基法・改善基準告示の教育を行っているか。※提出単位:事業者(1点→2点)
・国土交通省が公表している「貸切バス事業者の安全情報」において、全ての営業所の正規雇用の運転者の平均給与月額が最上位のランクであるか。※提出単位:事業者(新設:1点)
・法令で定められた健康診断以外の健康診断を受けさせているか。また、運転者の健康状態や疲労状況の把握等に効果の高い取組みを実施しているか。(2点→0点)
・運転者の健康状態や疲労状況の把握等に効果が高い携帯型心電計、居眠り警報装置等の機器を1台以上導入しているか。※提出単位:事業者(新設:1点)
・健康起因事故防止対策として有効な「睡眠時無呼吸症候群」「脳血管疾患」「心臓疾患・大血管疾患」「視野障害」に対する検査を実施し健康管理を行っているか。※提出単位:事業者(新設:8点)
次の①~④で各2点
①睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル
②脳血管疾患対策ガイドライン
③心臓疾患・大血管疾患対策ガイドライン
④視野障害対マニュアル
配点基準の変更③運輸安全マネジメント取組状況(配点20点→25点)
運輸安全マネジメント取組状況における配点においては、事業規模毎による評価基準ではなく、事業所は全て同じ評価基準とし、中小規模事業者と準大規模・大規模事業者との配点の差がなくなりました。
輸送の安全に関する研修等を実施しているか。(2点→7点)
具体的には、下記が変更されました。
【評価基準10】配点1点
運転者に対して、安全運行に必要な教育・訓練を定期的に実施し、記録しているか。
【配点基準11】配点2点
経営者は、安全に係る者に、外部機関が主催する輸送の安全に関する研修会・講習会等を受講させているか。
(1) 国土交通省の認定セミナーを受講した場合は2点
(2) 国土交通省の認定セミナー以外の受講は1点
【評価基準12】配点3点
運転者の安全に資する技能(運転実技)等の向上に努めているか。
より高度な実技訓練を実施している場合は3点、それ以外は2点
<例>より高度な訓練
・安全運転中央研修所、クレフィール湖東等専門機関での訓練
・雪上での走行訓練
・山岳道路(長い下り坂等)での走行訓練
【評価基準13】配点1点
運転者に対して次の内容の教育及び研修を実施しているか。
・運転者等の年齢、経歴、能力に応じたもの
・一方的な講義ではない方式(知識普及、問題解決、参加体験型)
配点基準の変更④違反(行政処分)の実績と事故の実績
違反(行政処分)の実績に対する変更はありません。しかし、事故の実績に対する配点は大きく変わっています。変更前は配点10点を上限に累積違反点数に応じて減点していたものの、変更後は上限を無くし、累積違反点数に応じて無制限に減点されます。
変更前:行政処分の違反点数に応じて最大10点の減点
変更後:行政処分の違反点数に応じて、10点を超える減点を行う
参考:評価項目及び配点変更一覧
配点基準の変更【まとめ】
セーフティバスの配点基準が変更されたことにより、貸切バス事業者はより安全管理の実効性強化が必須となりました。行政処分の影響も厳しくなり、研修や訓練の充実性が重要視されます。しかし、先進安全装備や健康管理対策の導入は事業者イメージや顧客信頼の向上、長期的なコスト削減につながったり、中小・大手問わず同じ基準で評価されるようになることで事業規模に関係なく公平な評価を得られるといったメリットもあります。
書類上で終わらず、実際の安全対策と法令遵守を高いレベルで維持し続けることが、認定獲得や事業存続に不可欠となります。
①違反(行政処分)の実績 <配点10点>
②事故の実績 <配点10点>
③安全性に対する取組状況(上位事項) <配点40→55点>
④運輸安全マネジメント取組状況 <配点20→25点>
合計 配点100点
法令順守で稼げていた20点はどこで補えばいい?

法令遵守で評価されていた20点分の配点が廃止された結果、事業者はより実践的な安全対策や管理体制の強化でその分を補う必要があります。特にドライバー教育の充実、健康や労務管理の見直し、先進安全装置の導入が重要なポイントです。
ドライバーの教育・研修の充実化
運転者教育は、安全運行の土台です。日々の業務の中で、法律の知識と実務スキルをバランス良く身につけることが、事故防止につながります。
全従業員が、労働時間や休息期間に関する正しい知識を共有することで、法令違反や過労運転を未然に防げます。また、継続的な研修によって、運転者や安全管理者の知識や意識の質が上がり、現場での判断力や対応力の向上につながります。
①労基法・改善基準告示の教育徹底(2点)
全従業員に対し、2年連続で労基法・改善基準告示の教育を行い、記録する
②輸送の安全に関する研修等を実施しているか(計7点)
・運転者に対して、安全運行に必要な教育・訓練を定期的に実施し、記録しているか。
・経営者は、安全に係る者に、外部機関が主催する輸送の安全に関する研修会・講習会等を受講させているか。
(1) 国土交通省の認定セミナーを受講した場合は2点
(2) 国土交通省の認定セミナー以外の受講は1点
・運転者の安全に資する技能(運転実技)等の向上に努めているか。
・運転者に対して次の内容の教育及び研修を実施しているか。
(1)運転者等の年齢、経歴、能力に応じたもの
(2)一方的な講義ではない方式(知識普及、問題解決、参加体験型)
③運行記録計またはデジタルタコグラフを活用した教育を行っているか。(2点)
④全乗務員に対する安全に関する教育実施計画を策定し、定期的に教育を実施しているか(2点)
⑤ドライブレコーダーから取得したデータを基に教育・指導を行っているか。(1点)
健康管理・労務管理の見直し
高齢化や過労による事故を防ぐためには、健康面のリスクを可視化し、事前に対応できる体制の整備が求められます。
①適齢診断の受診頻度:法令よりも多い頻度で適齢診断を受けさせている(2点)
国土交通大臣が認定する「適齢診断」を65歳以上75歳未満の全運転者に対し2年に1回以上受診させているかが評価対象となります。
②健康起因事故防止対策の検査体制(8点)
「睡眠時無呼吸症候群」「脳血管疾患」「心臓疾患・大血管疾患」「視野障害」すべてについて計画的に検査・健康管理をしているかが評価対象となります。
③健康状態や疲労状況の把握(健康診断以外)(1点)
運転者の健康状態や疲労状況の把握等に効果の高い取組を実施しているかが評価対象となります。
④運転者の平均給与水準(1点)
全ての営業所において「貸切バス事業者の安全情報」の運転者の平均給与の水準が最上位のランクとなっているかが評価されます。
先進安全装置の導入
安全性の高い車両の導入を推進するため、衝突被害軽減ブレーキを中心とした先進安全装置(ASV)の装着率などが評価対象となります。
①衝突被害軽減ブレーキの導入率(4点)
衝突被害軽減ブレーキとは、前方車両や障害物を検知し、衝突の危険が高まった場合に自動的に原則・停止させる装置です。自社保有のバスに衝突被害軽減ブレーキがどの程度の割合で導入されているかが評価されます。
②衝突被害軽減ブレーキ以外のASV装置の導入(4点)
ASV機能のうち、PCS以外の装備を導入しているかが評価されます。対象装置は車間距離制御装置(ACC)や車両安定制御装置(ESC)、ドライバー異常時対応システムなどが該当します。
③高性能アルコール検知器(対面点呼)(2点)
対面点呼で使用できる精度の高い検知器を導入しているかが評価されます。アルコール検知器から測定データが即時に営業所に転送され、点呼日時や乗務員氏名、検知結果が保存されるなど高性能タイプを使用することが条件となります。
グッドラーニング!活用で加点を狙う!

2025年度からのセーフティパス評価制度では、実効性ある安全対策が評価のカギになります。特に重要なのが、上述した「ドライバーの教育・研修」「健康・労務管理の強化」「先進安全装置の導入」の取り組みです。
グッドラーニング!は、トラック業界に特化した、実務に直結するe-ラーニング型教育サービスです。法令遵守や事故防止を目的とした各種講座が揃っており、国土交通省指定の安全指導教育にも対応しています。スマホやPCで手軽に受講できるため、事業者・運転者双方にとって効率的かつ継続しやすい教育環境で学べます。
現場に合わせて無理なく、効率良く加点対策を進めたいなら、グッドラーニング!が最適です。教育と記録の見える化で、セーフティバス評価にしっかり繋げましょう。
グッドラーニング!活用による評価対策
下記お役立ち資料では、貸切バス安全性評価認定制度(セーフティバス)評価制度の変更について分かりやすくまとめています。また、グッドラーニング!でカバーできる主な加点項目についても記載していますので、ぜひご覧ください!

貸切バス安全性評価認定制度(セーフティバス)の配点基準と加点対策まとめ
2024年度に改定されたセーフティバス評価制度の変更点と対策について図やイラストを用いて分かりやすくまとめた資料です。
資料ダウンロード(無料)はこちらまとめ

2025年度から、セーフティバスの審査基準が大きく見直されました。これまでのように書類を整えるだけの対応では、高評価を得ることが難しくなり、形式的な安全管理から、実効性のある安全対策への転換が求められます。
今後はドライバー教育や健康・労務管理・先進安全装置の導入といった取り組みを、どれだけ継続的かつ体系的に実施しているかが重要です。セーフティバス認定を目指す事業者は、早めの情報収集と計画的な体制整備を進めることが、信頼される運行と持続可能な経営への第一歩です。
当社の記事・お知らせに関する注意事項
- 最新の法改正・制度改正が必ずリアルタイムで記事に反映されているわけではありません。
- 情報を掲載するにあたり、事実と相違がないように注意しておりますが、絶対の正確性をお約束しているわけではありません。
- 掲載された情報の利用により何らかの損害が生じたとしても、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

