Useful Informationお役立ち情報
- 【グッドラーニング!】ホーム
- お役立ち情報
- 運送業の監査対策とは?必要書類や監査項目について解説
運送業の監査対策とは?必要書類や監査項目について解説
安全教育事業用トラック事業用バス

運送業の監査対象とは?運送業に対して行われる監査は、国土交通省の運輸局や運輸支局が行う調査を指します。重大事故や法令違反の通報、巡回指導時に悪質とみなされる法令違反が見つかった場合に行われる調査です。事故を未然に防いだり法令遵守の徹底を目的としています。今回は運送業の監査対象について必要書類や監査項目について解説します。
- 【勘違いが多い!】監査と巡回指導の違い
- 運輸局における監査の種類
- 監査が入る理由(端緒)
- 運輸局による監査の内容(重点事項)
- 監査実施後の流れ
- 監査による行政処分の種類と内容
- 安全教育を怠った場合のリスク(指導監督義務違反)
- 監査の対策方法とは
- まとめ
【勘違いが多い!】監査と巡回指導の違い
そもそも監査と巡回指導の違いをご存じでしょうか?運送業に対して行われる「監査」と「巡回指導」の内容は、それぞれ異なります。事前通知や行政処分の有無など大幅に異なるため、しっかりと違いを理解しておきましょう。
監査とは
監査とは、国土交通省の運輸局や運輸支局が行う調査です。重大事故や法令違反の通報、巡回指導時に悪質とみなされる法令違反が見つかった場合に行われます。監査に関する事前告知はなく、突然調査官が現れて監査する仕組みです。調査の際に違反項目があれば数日かけて監査が行われる場合もあります。調査結果により違反が発覚した場合は、行政処分が下されるので事前の準備が重要です。
巡回指導とは
巡回指導とは、トラック協会(適正化事業実施機関)が行う調査です。運送業を開始して1ヶ月から6ヶ月の間に行われることが多く、この時A判定となれば2、3年に一度のペースで実施されます。事前通知は2~3週間前に郵便で届き、突然循環指導が行われることはありません。巡回指導の際に違反項目があれば指導、業務改善が求められます。しかし、評価がA~EのうちDまたはE評価だと運輸支局に通報され、監査対象となる可能性もあるので注意しましょう。
| 監査 | 巡回指導 | |
|---|---|---|
| 調査機関 | 国土交通省の運輸局や運輸支局 | トラック協会(適正化事業実施機関) |
| 調査されるきっかけ | ・重大事故や法令違反の通報があった場合 ・巡回指導時に悪質とみなされる法令違反が見つかった場合 |
・運送業を開始して1ヶ月〜6ヶ月の間 ・上記期間でA判定になれば2、3年のペースで実施 |
| 事前通知 | ・基本的に調査官が突然現れる ・事前通知がされることもある |
・2~3週間前に郵便で届く ・突然巡回指導が行われることはない |
| 調査期間 | 違反項目があれば数日かかる | 3時間程度で終了 |
| 調査結果 | 違反が発覚すれば行政処分が下される | ・違反項目があれば指導が入り行政改善を求められる ・評価がA~EのうちDまたはEの場合、運輸支局に通報され監査の対象となる可能性もある |
運輸局における監査の種類

運輸局における監査は3種類あります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
特別監査
1つ目は「特別監査」、通称「トッカン」です。引き起こした事故または疑いのある法令違反の重大性を考慮し、厳格な対応が必要と認められる事業者に対して行われます。後述する一般監査のように重点事項を定めて行われるものではなく、全般的な法令遵守状況を確認する監査です。事前の通告なく突然行われますが、通知ありの場合もあります。
一般監査
2つ目は「一般監査」です。特別監査に該当しないもので、重点事項を定めて法令遵守状況を確認しますが、この重点事項は、監査をするきっかけとなったものに応じて決まります。一般監査を実施した事業者において、全般的な法令遵守の状況を確認する必要があると認められた場合には、特別監査に切り替えることもあります。特別監査同様、基本的には事前の通告なく突然行われるものです。中には事前に通知されて行われる場合もあります。
街頭監査(当面はバスが対象)
3つ目が「街頭監査」で、事業者自動車の運行状況や実態を確認するため、街頭で事業者を特定せず行う監査のことです。抜き打ちチェックのような監査とも言え、基本的にはバス事業者に向けて発着場などで行われます。
監査が入る理由(端緒)
実際に監査が入ってしまうきっかけにはどのようなものがあるでしょうか。運送業における監査は、以下の項目をきっかけに実施されます。
- 法令違反の疑いがある事業者
- ドライバーが死亡事故を起こした時
- ドライバーが悪質な違反をした時
- 事業への改善報告を行わなかった事業者
- 巡回指導を拒否した事業者
- 福利厚生が整備されていない事業者
- 最低賃金法に違反した事業者
- 3年間で3回以上同じような事故を起こした事業者
- 輸送の安全確保体制が整っていない事業者
- 受委託者に違反があった時
これらの項目の中で、社会的に影響力が大きい事故、特に悪質とみなされる違反を起こした事業者には「特別監査」が実施されます。それ以外の場合は基本的に「一般監査」が入る仕組みです。
運輸局による監査の内容(重点事項)
監査は、帳票類や車両を点検後、従業員への質問等をして事情を聴取、これらの結果を踏まえて監査結果を事業者に伝えます。監査で確認される重点項目は、国土交通省によって定められている下記8点です。ただし街頭調査・呼び出しによる監査を除きます。監査のきっかけとなった事情によっては下記以外も加わるので注意しましょう。
- 事業計画の遵守状況
- 運賃・料金の収受状況
- 損害賠償責任保険(共済)の加入状況
- 自家用自動車の利用、名義貸し行為の有無
- 社会保険等の加入状況
- 賃金の支払い状況
- 運行管理の実施状況
- 整備管理の実施状況
この中でも、特に「④自家用自動車の利用、名義貸し行為の有無」「⑦運行管理の実施状況」「⑧整備管理の実施状況」で違反があると重い処分になる可能性もあるため、十分注意してください。
①事業計画の遵守状況
運送業の許認可を取った際に作成、運輸局に提出した事業計画に沿って事業が実施されているか、重点的にチェックします。以下の情報が届出時と異なる場合は、所定の変更手続きが行われているか確認が入るのでしっかり確認しておきましょう。
- 事業計画に記載した営業所の名称や住所
- 休憩室の住所と広さ
- 車庫の住所と広さ
- 営業所に配置されている事業用自動車の数
- 法人役員
②運賃・料金の収受状況
届出を受けた料金表通りの運賃受け取りができているかを、請求書や通帳を見て細かくチェックします。現状の運賃が提出した料金表と合っていない場合は、早急に内容を変更しましょう。
③損害賠償責任保険(共済)の加入状況
対人無制限、対物200万円以上の自動車任意保険や交通共済などの「損害賠償責任保険」に加入しているかを確認されます。高いからといって保険に加入していない事業者は、今すぐ加入しましょう。
④自家用自動車の利用、名義貸し行為の有無
自家用自動車を利用した違反な営業類似行為、車両の名義貸し行為が行われていないかをチェックされます。
⑤社会保険等の加入状況
働く従業員が社会保険(健康・厚生年金)、雇用や労災を含む労働保険に加入できているかをチェックされます。
⑥賃金の支払い状況
長時間労働や賃金未払いなどを防ぐために、従業員から内部告発があれば監査が実施される場合もあります。労働時間や賃金の支払い状況が不適切だとされた場合は、行政処分の対象となりますので注意しましょう。
⑦運行管理の実施状況
過労運転防止の観点から、運行管理に関する業務が不備なく実施されているかを、運転日報や点呼記録を元に厳しくチェックされます。こちらは監査の中でも特に重要な項目となるため、必ず不備なく記録・管理しましょう。
⑧整備管理の実施状況
「車両台帳」の整備や記録が正しく実施されているかをチェックされます。3か月または12か月ごとに定期点検基準を作成し、それに基づいた点検、点検整備記録簿の保存が義務付けられています。
監査実施後の流れ

実際に監査を実施した場合、どのような流れになるのでしょうか?直前になって慌てないように前もって確認しておきましょう。
①監査の実施
基本的に、「特別監査」と「一般監査」は事前告知なく実施されます。なお、運転者の脳血管疾患や心疾患など事故速報対象となる監査の端緒など、労基署の臨検監査と同時に運輸局監査が行われる場合は、事前に監査日が知らされることもあります。
②改善指示書が届く
監査が終わると、事業者へ「確認書」が渡され「行政処分の対象となる法令違反」「行政処分の対象とならない警告」「行政処分の対象とならない指導」に分けられ、監査実施後の違反内容について告げられます。この時点で違反していないと思うことがあれば、すぐに監査官に伝えましょう。
③弁明の機会付与(弁明書の提出)
監査実施から2〜3ヶ月後に、違反事項と処分内容について記載された弁明通知が届きます。この時違反について不服がある場合は、弁明通知に必用事項を記載し提出しましょう。
弁明の機会に提出する弁明書について、必ず提出する義務はありません。あくまで違反事項に対する弁明の機会があるだけなので、反論の必要がなければ弁明書の提出はしなくて良いのです。なお、弁明書の提出期間は2週間なので、弁明書を提出する際は前もってある程度反論の方針を検討しておきましょう。
④輸送施設の使用停止及び附帯命令書が届く
日車の場合、弁明通知が届いた後、約1ヶ月後に行政処分の内容が決まります。その後行政処分の内容が記載された輸送施設の停止および付帯命令書が届くので、内容を確認しましょう。同時に、運輸局から処分内容を告げる電話が入ります。
⑤ナンバーの返還(領置)又は営業停止【行政処分】
日車の場合、運輸局から電話が入った後、営業所轄館の運輸支局へ、1週間以内に指定された車両のナンバープレートと車検証を持参します。
⑥呼出監査及び改善報告書の提出
行政処分が終わったら、運輸支局から改善報告書が届きます。それから2ヶ月後を目処に呼び出し監査が実施される流れです。改善事項を全て改善の上、日報・点呼簿など指定された書類と併せて改善報告書を持参し、運輸局へ提出してください。全ての違反事項が改善されていると認められたら、呼出監査は終了です。
監査による行政処分の種類と内容
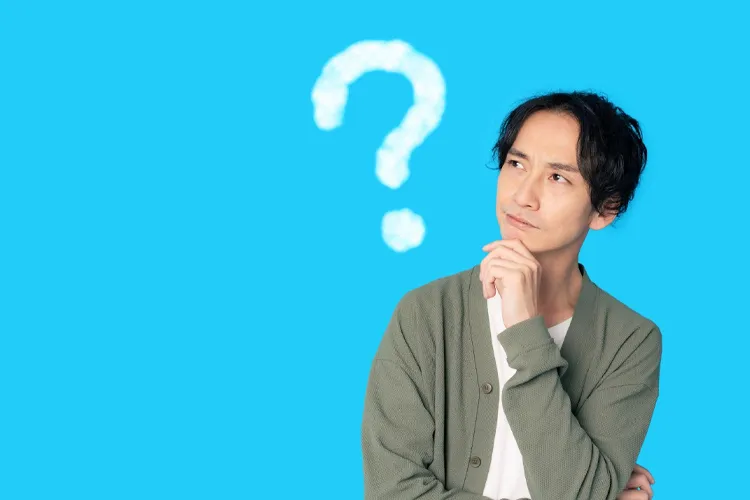
監査によって行政処分を受けてしまった場合はどうなるのでしょうか。行政処分等に至らない、軽微なものから順に「口頭注意」「勧告」「警告」があります。
- 勧告:勧告書の交付のみ/トラックの運転は可能
- 警告:警告書の交付のみ/トラックの運転は可能
そのほか、下記行政処分の種類と内容を詳しく見てみましょう。
①自動車その他の輸送施設の停止(トラックを動かすことの禁止)
使用停止となる車両台数は、営業所に配置されているトラック数によってことなるため、詳細は以下を確認してください。
| 処分日数 | 所属するトラックの数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1両~10両 | 11両~30両 | 31両~60両 | 61両~100両 | 101両以上 | |
| 30日車まで | 1両 | 1両 | 1両 | 1両 | 1両 |
| 31~60日車 | 1両 | 2両 | 2両 | 3両 | 3両 |
| 61~100日車 | 1両 | 2両 | 3両 | 5両 | 5両 |
| 101~300日車 | 2両 | 3両 | 5両 | 8両 | 10両 |
| 301日車以上 | 3両 | 3両 | 5両 | 10両 | 15両 |
出典:運送会社の行政処分と違反点数制度をわかりやすく解説【最新版】 | ⾏政書⼠法⼈シフトアップ(名古屋)
②事業の停止処分(営業停止)
事業停止(営業停止)とは、悪質または重大な法令違反を犯した時に、一定期間運送行為が行えなくなる行政処分です。事業停止となるのは非常に悪質な事業者だけで、事業停止処分になると、違反した営業所は、30日間運送業を行えません。
また、違反点数の累計が51点〜80点となった場合、違反行使のあった営業所管轄区域内全ての営業所が事業停止になります。
悪質または重大な法令違反は、以下の通りです。
- 運行管理者の未選任
- 整備管理者の未選任
- 全運転者に対して点呼未実施
- 監査拒否、虚偽の陳述
- 名義貸し、事業の貸渡し
- 乗務時間の基準に著しく違反
- 全ての車両の定期点検整備が未実施
③許可の取り消し処分
許可の取り消し処分とは、言葉通り運送業の許可が取し消しになってしまう処分です。以下に該当する場合許可取り消しになります。
■公表すべき内容
①輸送の安全確保命令、事業改善命令、自動車その他の輸送施設の使用停止処分、事業停止処分
②当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容(改善報告書等)
■公表場所
本社及び当該行政処分を受けた営業所
■公表手段
以下の手段の中から適切なものを選択
①自社ホームページへの掲載
②報道機関へのプレス発表
③自社広報誌等への掲載
④営業所等利用者が出入りする自社施設における掲示
③旅客自動車運送事業者の場合は、事業用車両内における掲示等
安全教育を怠った場合のリスク(指導監督義務違反)

安全教育を怠った場合のリスクは、前述した行政処分の他にも多数あります。行政処分を受けなかったとしても以下のリスクがあるので、監査対策をしっかりと行いましょう。
国土交通省HPにて「行政処分事業者」として公開(5年間)
行政処分を受けた事業者は、国土交通省の自動車総合安全情報ページで公表しなければなりません。運送業の健全な発達および輸送における安全確保のため、バスやタクシー、トラックを利用する際の、事業者における利便性を図るために行政処分の状況が過去5年分公開されます。
自社での公表義務(3年間)
行政処分を受けた事業者は、自社のHPや報道期間へのプレスリリースにて指導監督義務の違反を公表する必要があります。公表期間は処分を受けた日から3年間です。公表すべき処分内容などの詳細は以下となります。
(1)累積違反点数超え①
・事業停止処分を過去2年間に3回受けていた事業者が以下のいずれかに該当する場合
・累積違反点数が30点以下の場合で、270日車以上の車両停止処分を付された
・累積違反点数が31点以上の場合で180日車以上の車両停止処分を付された
・累積違反点数が51点以上となった
(2)累積違反点数超え②
・一つの管轄区域内で累積点数が81点以上になった時
(3)命令に従わない
└車両使用停止処分または事業停止処分を受けた事業者が、自動車検査証の返納や登録番号の返納命令に従わない時
(4)3年以内に事業停止処分となる行為の反復
└事業停止処分を受けた事業者が、処分を受けた日から3年以内に同一の悪質または重大な違反を行った時
(5)同一命令違反
└以下の行政処分を受けた事業者が3年以内に同じ違反をした時
・事業計画に従い業務を行うべき命令
・安全管理規定の変更命令
・輸送の安全の確保命令
・公衆の利便を阻害する行為の停止命令
・事業改善命令 など
(6)旅客運送を行った
└許可がないのに、継続または反復して、かつ有償で旅客運送を行った時
引用:貸切バス 行政処分は公表しなければならない? | 行政書士法人ココカラザウルス
Gマークへの影響
事業者の安全取り組みを可視化した「Gマーク」への影響も避けられません。Gマークをつけて走ることで常に見られている意識が生まれ、ドライバーにプロの模範である自覚が生まれます。結果的に安全運転への意識も高くなるのです。また、これまで曖昧だった安全対策ですが、Gマークの取得をきっかけに明確化されるため、事業者全体で統一した安全管理方法も根づきます。
このように、Gマークは運送業において欠かせない存在ですが、指導監督義務違反をしてしまうと、新規取得や更新ができなくなる場合もあるのです。車両使用停止処分の場合、以下の処分が下されます。
車両停止の処分日数10日車までごとに1点が加算されます。違反点数は基本的に3年間で消えますが、監査実施により行政処分を受け、その後3年以内に再違反をした場合は処分日数が倍になり、加算される違反点数も倍となります。
Gマークの申請において、違反による点数が20点を超えると行政処分(違反)の実績評価が0点になります。事故の実績がゼロで20点を取ったとしても、事故や違反における状況項目の基準点に達しないため、Gマーク申請が却下されてしまうのです。
監査の対策方法とは
指導監督義務違反にならないためにも、今からできる監査対策をしっかりと行っておくことが大切です。
特に重視したいのが「一般的な指導及び監督」で、毎年実施しなければならないことから「年間教育」と呼ばれています。
「一般的な指導及び監督」の実施状況における監査ポイントは次の通りです。
- 指導及び監督の実施計画が作成されているか
- 指導・監督指針の内容を網羅しているか
- 実施状況が正しく記録、保存されているか
詳しく見ていきましょう。
①指導及び監督の実施計画が作成されているか
事業者は、一年間を通じて定期的かつ継続的に指導監督を実施しなければならず、その計画をまとめた「基本計画表」を作成する必要があります。
計画表には実施時期・指導項目・内容を明記し、全ドライバーに周知しなければなりません。
②指導・監督指針の内容を網羅しているか
国土交通省告示第1366号に定められている「一般的な指導及び監督の指針」は次の通りです。
1、事業用自動車を運転する場合の心構え
2、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
3、事業用自動車の構造上の特性
4、貨物の正しい積載方法
5、過積載の危険性
6、危険物を運搬する場合に留意すべき事項
7、適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況
8、危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
9、運転者の運転適性に応じた安全運転
10、交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法
11、健康管理の重要性
12、安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法
ドライバーへ理解させるべき事項が各12項目ごとに定められており、国土交通省は「一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を公表、指針を示しています。
実施した指導内容が指導指針とは違うものであったり、不十分であった場合は指導監督を行っていないと見なされ「指導監督の未実施」となることもあるので正確に実施しましょう。
指導監督に使用した資料は3年間の保存義務があり、監査の際に提示を求められることもあります。
③実施状況が正しく記録、保存されているか
指導監督を実施した日時や場所、内容や指導そして監督を行った者と受けた者を記録しなければなりません。
いわゆる「指導記録簿」と呼ばれる記録で、営業所において実施日より3年間保存する必要があります。
まとめ

運送業に対して行われる監査は、国土交通省の運輸局や運輸支局が行う調査です。重大事故や法令違反の通報、巡回指導時に悪質とみなされる法令違反が見つかった場合に行われ、事故を未然に防いだり法令遵守の徹底を目的としています。
運送業を運営する上で、従業員の安全教育は欠かせません。特に従業員が多い事業者様は、業務の調整や受講状況の管理にも悩まされていることでしょう。そこでおすすめなのがeラーニングです。
時間と場所を選ばずに、全てのドライバー・乗務員に対して効率よく指導教育を実施できます。待機時間を利用しての受講も可能で、クラウド型の教育システムのためタブレットやスマホ、パソコンなどを使って場所を選ばずに受講できます。管理用サイトがあるため、受講者ごとの受講状況やテスト結果も、レポートで確認できるので管理の手間もありません。
ドライバーに対する安全教育を効率よく行いたい事業者様は、ぜひeラーニングをご検討ください。
当社の記事・お知らせに関する注意事項
- 最新の法改正・制度改正が必ずリアルタイムで記事に反映されているわけではありません。
- 情報を掲載するにあたり、事実と相違がないように注意しておりますが、絶対の正確性をお約束しているわけではありません。
- 掲載された情報の利用により何らかの損害が生じたとしても、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

